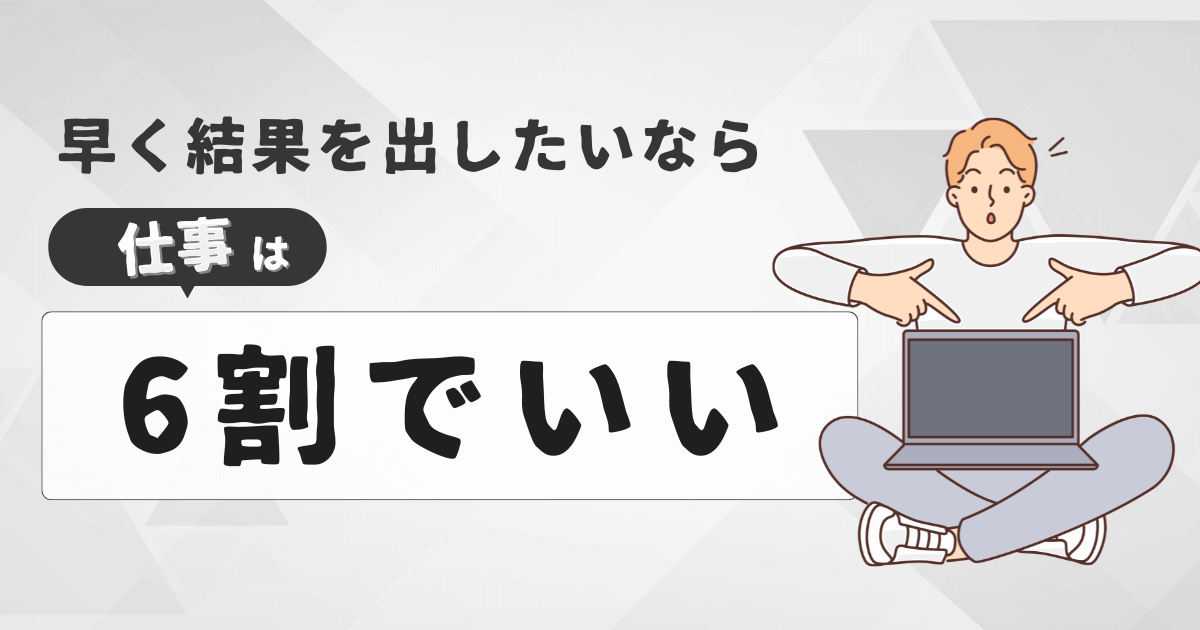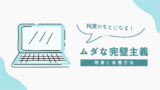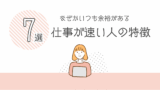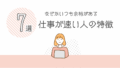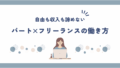資料作成にこだわりすぎて時間がかかる。「もっとちゃんとやらなきゃ」と自分にプレッシャーをかけている……。
真面目で責任感のある人ほど、常に全力で仕事に取り組もうとします。しかし、ずっと100%の力で走り続ける働き方には、限界があります。疲弊すれば思考力や判断力も落ち、ミスが増えます。成果を出しているように見えて、効率が悪い働き方になっていることも少なくありません。
実は、「あえて6割の力で取り組む」という選択が、効率的に成果を上げ、ストレスを減らすための鍵になることもあるのです。本記事では、仕事を6割で出すメリットと6割で進めるためのコツを解説します。
「仕事は6割でいい」と聞いて、どう思いますか?
「仕事は6割でいい」と聞くと、「そんな甘くない」「中途半端な仕事では通用しない」などと感じた方も多いかもしれません。確かに、仕事とは責任が伴うものであり、成果や品質が求められるものです。
しかし一方で、「常に全力で完璧を目指すこと」が、かえって非効率になってしまう場面も多くあります。
たとえば以下のような経験はないでしょうか?
- 納得いくまで資料を作り込みすぎて、提出が遅れる
- 「もっとよいアイデアがあるはず」と考えすぎて、手が止まる
- 細部にこだわるあまり、ほかの業務に手が回らなくなる
実は、こうした完璧主義こそが仕事の停滞を招いてしまうことは多々あります。「仕事ができる」「仕事が速い」と言われる人たちは、完璧主義はやめて、もっとラクに、もっと身軽に仕事をこなしています。
「6割で動く」だけでここまで違う。成果につながる4つのメリット
完璧を目指そうとしていつまで経っても作業が終わらない状態は、「自分で自分の首を絞める働き方」です。一方で、「6割でまず動く」というスタンスには、次のようなメリットがあります。
スピード感が出る
完璧を求めるあまり、作業のスタートが遅れたり、ひとつの作業に時間をかけすぎたりすることがあります。これにより、最初は順調に進んでいるように見えても、次第に仕事全体のスピードが落ちてしまいます。さらに、遅れが出ると、ほかのタスクにも影響が出るため、全体の進捗が停滞してしまうことがよくあります。
しかし、6割の段階でまずアウトプットすることで、最初からスピード感を持って仕事を進めることができます。
スピード感が生まれる理由は以下の通りです。
- 早期の着手:6割の段階でアウトプットをすることで作業が早期に進み始めます。時間をかけすぎず、適切なタイミングで次のステップに進むことができます。
- 進捗の可視化:仕事が進んでいる実感を得ることで、進捗を可視化し、達成感を感じることができます。これにより、作業のモチベーションが高まります。
- 周囲の信頼獲得:仕事が遅れずにスピーディに進んでいくことは、周囲からの信頼や安心感を生みます。「この人は動きが速い」と評価されることで、次の仕事にもスムーズに取り組むことができます。
- 精神的な余裕:タスクが停滞していると、精神的に圧迫感を感じることがあります。スピード感を持って進めることで、余裕を持ちながら仕事に取り組むことができます。
結果として、完璧を求めて時間をかけすぎるよりも、6割で進めながらもスピーディに仕事を進めるほうが仕事全体の効率が高まります。最終的に成果も高品質なものに仕上がります。
相手からのフィードバックが早くもらえる
仕事は一人で完結することが少なく、チームメンバーや上司、顧客からの意見を反映させることが必要不可欠です。特に、企画書や資料、デザイン、プランといったものは、最初の段階での共有が非常に重要です。
早い段階でアウトプットを共有することで、他者の視点を早期に取り入れることができます。
たとえば、プロジェクトが進行するにつれて、見落としがちな要素や方向性のズレに気づくことができます。これにより、「方向性がそもそもズレていた」という最悪のシナリオを防ぐことが可能です。
さらに、フィードバックを受け取ることで、次のステップに進む前に問題点を解決できます。修正や改善が加速し、最終的に質の高い成果物を迅速に仕上げることにつながります。

完璧に仕上げることを目指すよりも、早めにアウトプットし、フィードバックを得るほうが、結果的に質の高い成果を迅速に得られるのです。
やり直しがあっても早い段階で軌道修正できる
最初から完璧な成果物を目指して時間をかけすぎると、後で方向が間違っていたことに気づいた際、修正にかかるコストが非常に大きくなります。これが後々の負担となり、結果的に時間やリソースを無駄にしてしまいます。
一方で、6割の段階で仕事を出すことで、仮に方向性が間違っていたとしても、早い段階で軌道修正を行うことができます。
早い段階で修正を加えることには以下のメリットがあります。
- 軽微な手戻り:完璧を目指さずにまず6割で出すことで、もし方向性がずれていた場合でも、修正の範囲が小さく、手戻りが少なくて済みます。この段階であれば、再調整もスムーズに行えるため、作業全体の遅れを最小限に抑えることができます。
- リスクヘッジ:早期に間違いに気づけるということは、重大なミスを防ぐためのリスクヘッジになります。方向性を見誤る前に問題を発見できることで、大きな修正や時間のロスを避けることができ、最終的に効率的に進めることができます。
- 具体的な修正点の明確化:早い段階で問題点を見つけると、「何が足りなかったか」「どう改善すべきか」が具体的に見えてきます。これにより、修正がただの手戻りではなく、学びと成長につながります。次回同じような場面に直面した際には、より効果的に対応可能です。
- 改善のサイクル:6割で出してフィードバックを受けることで、改善のサイクルが早期に回り始めます。このサイクルの速さは、成果物を最終的により高品質に仕上げるために不可欠です。
「出すこと」自体のハードルが下がり、手が止まらない
完璧主義に陥ると、「100点で出さないといけない」という思い込みが、仕事の進行を妨げる大きなブレーキになります。たとえば資料を提出する前に何度も見直してしまったり、意見を言うことに対して不安を感じたり、タスクを進めるのに時間をかけすぎてしまったりすることがよくあります。
これが続くと、結果として 「出せない」「言えない」「進まない」 といった悪循環に陥ります。
6割の段階でまずアウトプットすることで、このような心理的なハードルを大きく下げることができます。完璧でなくてもまず出してみるという行動が、無意識のうちに心の中で「大丈夫、OK」という許可を与え、手を止めずに作業を進めることが可能になります。
「6割でまず出す」を可能にするコツ
実際に「6割の力でまず動く」にはどうすればいいのでしょうか?ここでは、実践的なポイントを解説します。
完成度ではなく「進行度」を意識する
資料や提案などは、完成してから出すのではなく、大枠ができたら一度出すという意識が大切です。
たとえば以下のような状態で出すことが考えられます。
- 資料:骨組みだけでもスライド化して共有し、全体の流れや方向性を早めに確認してもらう。
- アイデア:3割の思いつきを言語化し、初期の段階で反応をもらってさらにブラッシュアップする。
- 記事:構成だけでも相手に見せ、内容が適切か、視点がずれていないかを早い段階でチェックしてもらう。
この段階で意見をもらうことで、最終的な成果物にズレが生じにくくなります。逆に、完成度を最初から追い求めると、フィードバックをもらうタイミングが遅れ、方向性を修正するのが大きな手間になります。
最初の段階で意見をもらいながら進めることで、成果物の質を高めるだけでなく、作業全体の効率化にもつながります。
「ドラフト前提」で共有する習慣を持つ
「仮の案です」「叩き台として出します」と伝えることで、相手の期待値をコントロールし、以下のメリットを得ることができます。
- チームワークが強化される:みんなで「ドラフト」を改善していくことで、チーム内での信頼が深まり、より高い成果を出せるようになります。
- 期待値を調整できる:完璧を求められていないことを伝えることで、相手も無理な要求をせず、リラックスしたフィードバックがもらえます。
- 心理的な負担が減る:「ドラフト」という言葉を使うことで、完璧を目指さなくてもいいと自分に許可を出し、安心して作業に取り組むことができます。
チームや取引先との「合意形成の場」として活用する
6割で出すことは、単に手を抜くことではありません。それは、方向性をすり合わせるための「接点」や「起点」を早めにつくるという意味があります。
最初の段階でアウトプットを共有することで、チームや取引先との合意形成がスムーズになります。
たとえば提案やアイデアを最初に共有することで、早い段階でフィードバックをもらい、意見の違いを確認することができます。これにより、後々の手戻りを減らすことができ、作業の方向性が最初から一致していれば、後の修正作業が少なくて済みます。
また、合意形成が早期に進むことで、周囲との信頼関係も構築しやすくなります。相手も「早い段階で確認できる」「意見を反映しやすい」と感じることで、コミュニケーションが円滑になり、共同作業の効率も高まります。
力を抜ける場所があるから、力を入れるべきところに集中できる
すべての仕事を100%で仕上げる必要はありません。むしろ、「6割で十分な仕事」と「高い完成度が求められる仕事」を見極めることで、本当に注力すべき場面に時間とエネルギーを集中できます。
たとえば以下のように時間とエネルギーの配分が可能です。
- 社内共有用のメモは6割でOK
- 社外向け提案書は8割以上の完成度が必要
- 日報は最低限の内容で済ませる
- クロージングに近い商談は精度高く仕上げる

業務の重要度・影響力・関係者の期待値に応じて「どこまでやるか」を意識的に調整することで、成果につながる仕事に最大のリソースを割けるようになります。
まとめ
「仕事は6割でいい」という考え方は、頑張りすぎている自分をゆるめるヒントであり、効率的で柔軟な働き方につながる大事な考え方です。完璧を目指すのではなく、「まず動く」「早く出す」「育てていく」といったプロセスを意識しましょう。余力を残しておくことで、予期せぬトラブルにも冷静に対応でき、仕事が順調に回り出します。