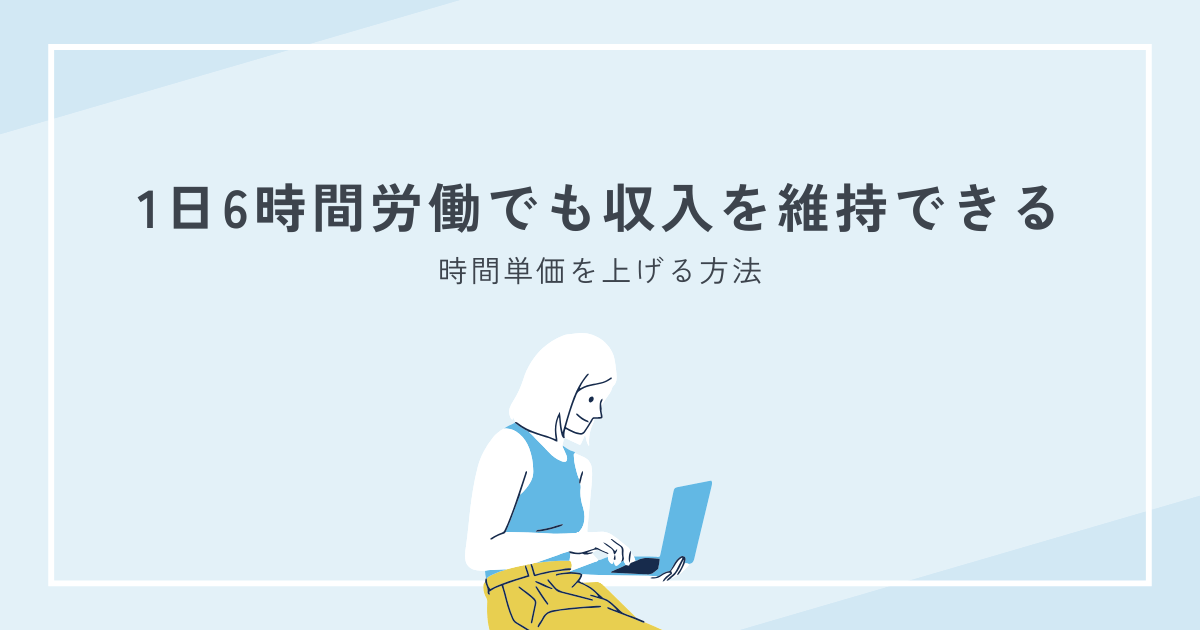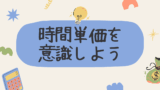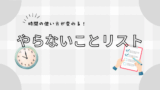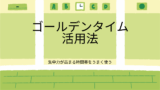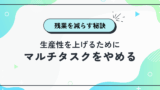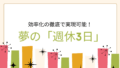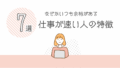もっと自由な時間が欲しいけど、収入は下げたくない……。このように思っている人は多いのではないでしょうか。かつての常識では「働く時間が少なければ収入も少ない」が当たり前でしたが、今は違います。時間の使い方と働き方の選び方次第で、1日6時間などの短時間でも収入を維持することは十分可能です。
筆者自身も会社員時代とフリーランス時代を通じて、働く時間を減らしながら収入を維持・向上させてきました。その経験をもとに、実現に必要な考え方と方法をお伝えします。
1日8時間労働は現代になじまない
一般的な企業の所定労働時間は1日8時間なので、少なくとも8時間は毎日働いている方は多いはずです。しかし、そろそろ「1日8時間働くことが当たり前」という考え方を捨てませんか?
そもそも世界的に1日8時間という基準が定着している背景は、イギリスの産業革命までさかのぼります。この時代の工場では1日12〜16時間労働が当たり前だったため、過酷な環境で働く労働者(子どもも含む)に対して労働時間の短縮を求める声が高まりました。
そこで登場したのが「8時間働き、8時間休み、8時間学び・楽しむ」という、1日24時間を3等分する考え方でした。これが後の労働運動に大きな影響を与え、アメリカやヨーロッパでも8時間労働制を求める運動が広がり、多くの国で法制化が進みました。
当時は画期的だった8時間労働ですが、今では「長すぎるのでは?」という見直しの声が高まっています。働き方の多様化やテクノロジーによる効率化を背景に、「6時間労働」や「週休3日制」など、新たな基準への模索が進んでいます。
また、人間の集中力が持続するのはせいぜい1日4〜6時間程度という研究もあります。にもかかわらず、長時間労働が当たり前のように続く社会では、疲れた頭で非効率に働き続ける時間が生まれがちです。
それならいっそ、「集中できる時間だけ働いて、成果を出す」ほうが理にかなっているのではないでしょうか。
1日6時間で働くことのメリット
1日6時間労働という働き方には多くのメリットがあります。自分の能力や時間を最大限に活かすことで、心身ともに充実した生活を実現しやすくなります。
集中力が維持しやすい
長時間働けば働くほど集中力は低下していくのが人間の脳の特性です。人間の集中力は1日4時間~6時間程度と言われています。これを超えて8時間、場合によっては残業で10時間近く働くとなると、どうしても「惰性で働く時間」「注意力が落ちた状態での作業」が増えてしまい、生産性は下がる一方です。

会社員の方は、職場を見渡してみてください。1日8時間を、本当に全集中で仕事に取り組んでいる方、どれくらいいますか?おそらく、ほとんどいないと思います。多くの人が、8時間のうち何時間かを、集中力が下がった非生産的な状況で取り組んでいたり、たばこ休憩や同僚とのおしゃべりなど仕事以外の時間に割いたりしているはずです。
結局、人間は8時間も働けるようにはできていないのです。
6時間労働であれば、集中力が高い時間帯にタスクをこなすことで、質の高いアウトプットが可能になります。結果的に、生産性も高まります。
プライベートや家族との時間が持てる
1日8時間労働だと、たとえ定時上がりだったとしても電車に乗って帰宅できる頃には夜になり、夜ご飯を食べてお風呂に入って終わってしまいます。
一方、1日6時間労働の場合、夕方になる前には仕事が終わり、そのあとの時間にゆとりができます。仕事帰りにゆっくり買い物をすることも、家族との食事や子どもとの時間、自分の趣味やリラックスの時間など、さまざまなことに充てられます。
ライフステージによっては、この時間の余裕が何よりの価値になることもあります。
副業や学習、趣味に時間を割ける
1日8時間勤務→6時間勤務にすることで生まれる2時間の余白を、副業やスキルアップの学習時間に充てることが可能です。
たとえば専門スキルを身につける時間に充て、そのスキルをもとに講師をしたり動画をアップしたりできます。その結果、本業以外に収入源ができ、将来的なキャリアの選択肢が増えます。
将来の収入アップやキャリア形成につながる活動を日常的に積み重ねられるのは、長期的なメリットです。
健康的な生活リズムが作れる
残業続きで不規則になりがちな生活習慣も、6時間勤務なら朝食・睡眠・運動の時間を確保しやすくなります。心身の健康が保たれることで、仕事のパフォーマンスも自然と向上します。
1日6時間で生活するための現実的な視点
1日8時間労働に慣れている人にとって魅力的な1日6時間労働ですが、実現のためには収入面や業務管理への対策が不可欠です。甘い理想だけで終わらせないために、現実的な視点を持って備えることが重要です。
収入が下がるリスクとどう向き合うか
労働時間を減らせば、当然ながら収入が下がるリスクが出てきます。
これに備えるには、副業での収入補填や、生活コストの見直しが現実的な対策です。月5〜10万円の副業収入でも、1日の労働時間を減らす後押しになります。
加えて、不要な固定費(保険・サブスク・通信費など)の見直しも有効です。
業務効率の重要性
6時間でこれまで8時間かけて出していた分の成果を出すには、効率よく働くことが前提です。
業務の優先順位づけや集中時間の活用、ツールやテンプレートの活用などを駆使し、「短時間でも成果が出せる人」になる努力が必要です。
「時間単価を上げる」考え方
収入を落とさずに労働時間を減らすには、「時間単価を上げる」意識が欠かせません。6時間で今までの収入を維持するためには、「自分の時間は高く売る」ことを常に意識することが重要です。
収入の基本は「労働時間 × 時給」で成り立っています。これは時給制のアルバイトに限らず、日給月給や年俸制の正社員でも根本的には変わりません。
すると、1日8時間働いていた人が6時間に減らした場合、単純に時給を上げないと収入は下がってしまいます。逆に、時給を1.3倍、1.5倍と上げていくことができれば、労働時間を減らしても収入はキープできます。
1日6時間労働にするために時間単価を上げる方法
時間単価を上げるための基本的な考え方は、「同じ時間でより多くの成果を出す」か、「より高い単価で仕事をする」ことです。ここでは、時間単価を上げるための現実的かつ実践的な工夫をご紹介します。
スキルの専門性を高める
汎用的なスキルよりも、特定分野に特化したスキルの方が単価は上がりやすくなります。
たとえば「Webマーケティングの中でも広告運用に強い」「会計知識とITスキルを掛け合わせて経理DXを推進できる」といったように、「この人にしか頼めない」という専門性を築くことが大きな武器になります。
顧客への提供価値を明確にする
成果や価値が見える形で伝わると、「この人に任せると成果が出る」と納得してもらいやすくなります。
たとえば提案書に過去の成果実績やビフォーアフターの例を添える、納品物にストーリー性を持たせるなど、価値を見える化する工夫が時間単価の引き上げにつながります。
交渉力・提案力をつける
「この金額でお願いします」と自信を持って提示できる力は、交渉力・提案力・実績から生まれます。
また、自分の強みを言語化し、相手にとっての価値に変換して伝える力も重要です。
交渉の場において「価格を決める側」に立てるかどうかが、時間単価のコントロール権を握る鍵を握ります。
作業の再利用・仕組み化を徹底する
非稼働時間も価値に変えることで、実質的に時間単価が上がります。
たとえば提案資料や作業手順をテンプレート化して再利用するといった工夫です。自動収益源(ブログ・note・YouTubeなど)を作り、働かなくても収益が出る時間を持つことも有効な方法のひとつです。
クライアント(または職場)を選ぶ
どれだけ努力しても「時間ではなく成果を見る」価値観がない相手では、単価の向上は難しいこともあります。そのため、成果を正当に評価するクライアントや会社を選ぶことが必要です。
また、「相性のよい相手に時間を使う」ことも、時間単価を高める戦略です。たとえば、特定の業界や分野において自分が強みを持っている場合、その分野の顧客と仕事をすることで、より高い価値を提供できます。
タイムマネジメント力を鍛える
限られた時間で最大の成果を出すにはタイムマネジメント力が欠かせません。詳細は後述しますが、具体的には以下のような工夫が可能です。
- タスクの重要度と緊急度で優先順位を明確に
- 集中力の高い時間帯に頭を使う仕事を集中させる
- マルチタスクを避け、1つの作業に深く集中する習慣をつける
これにより短時間で成果を出す力が磨かれ、単価交渉でも説得力が増します。
時間単価を上げるためにやったこと(筆者の実例)
筆者が実際に取り組んできた時間単価アップ施策は以下のとおりです。特別な才能があったわけではなく、地道な積み重ねで実現しました。
- 専門性の高い案件に取り組む
報酬の高い仕事に挑むことで、自然と単価が上がっていきました。具体的には、ライティングや校正の仕事を受注する際、テーマを「法律」に限定しています。社会保険労務士の資格を持っているので、資格で得た知識を活かせる仕事に特化するようにしました。 - 自動収入源を増やす
自己サイトを育て、一定の広告収入が入るようになったことで、時間を切り売りしない収入源が生まれました。これは精神的な安心感にもつながります。 - 時間の使い方を徹底的に見直す
無駄な連絡や作業を極力排除し、集中力の高い時間に価値の高いタスクを集中させることで、生産性を大きく上げられました。
誰でもできる効率化の工夫|6時間で8時間分の成果を出す方法
1日6時間勤務でも成果を落とさないためには、やみくもに働くのではなく、成果に直結する時間の使い方を意識することが重要です。限られた時間で最大限のパフォーマンスを出すには、以下のような日常的な工夫が効果的です。
タスクの優先順位をつける
まず基本となるのが、今やるべきことを見極める力です。
人はつい、目の前の「緊急だけど重要でないタスク(例:メール返信、雑務)」に反応してしまいがちです。しかし、本当に成果につながるのは「緊急ではないが重要なタスク(例:資料の改善、スキルアップ、仕組み化)」です。
この本質的な業務に時間を割けるよう、朝一番で1日のタスクを整理し、優先度を「重要度×緊急度」で分類してみましょう。特に重要なのは、「あとでやろう」と後回しにしがちなことほど、先に片づけることです。長期的に見ると、これが生産性と成長を大きく左右します。
加えて大切なのが、やらないことを明確にするという視点です。すべてのタスクをこなそうとするのではなく、成果に直結しない作業や、自分でやる必要のないことは思いきって手放す判断も必要です。
集中力のピーク時間帯に頭を使う仕事を入れる
人には「集中力のゴールデンタイム」があります。多くの人にとっては、朝の時間帯が脳の働きが最も高まる時間です。
この時間帯にメール処理や単純作業を入れてしまうのは非常にもったいないことです。代わりに、企画立案・資料作成・分析など、思考力を必要とする仕事を集中させましょう。
集中力が必要な仕事とそうでない仕事をあらかじめ分類しておき、「自分の脳が冴えている時間帯には頭を使う仕事だけをやる」という意識づけをするだけでも、1日の成果は大きく変わります。
ツールやテンプレートでルーチンを自動化
日々の仕事の中には、内容は違っても「やっていることは同じ」というルーチンワークが多く存在します。これを毎回ゼロから対応するのではなく、テンプレート化・自動化しておくことで、時間と労力を大きく削減できます。
たとえば以下のような工夫が可能です。
- よく使うメールの文章はテンプレート化して定型文登録
- 資料作成はフォーマットを統一し、項目を埋めるだけにする
- タスク管理はNotion・Trello・Googleカレンダーなどで可視化
- 定例業務はチェックリスト化して、思考の負荷を減らす
こうした仕組み化を積み重ねることで、単純作業に使う時間が減り、本来注力すべき業務に時間を回せるようになります。
マルチタスクは排除し、シングルタスクで集中
「ながら作業」は、効率的に見えて実は生産性を大きく下げる要因です。複数のタスクを同時に処理しようとすると、脳は常にタスクの切り替えを行い、集中力が分散します。その結果、どの仕事も中途半端になりがちです。
生産性が高いのは、1つのタスクに一定時間だけ集中し、それが終わってから次に進むシングルタスクのスタイルです。
たとえば「この30分は資料作成だけに集中」「メール確認は1日2回だけ」と時間をブロックしておくと、周囲の雑音や誘惑に流されず、深い集中状態(=フロー状態)に入りやすくなります。
また、スマホや通知の音は集中を阻害する大敵です。集中したいときは通知をオフにする、スマホを手元に置かない、というルールをつくると、より没頭しやすくなります。
仕事選び・働き方選びのポイント
時間単価を上げて効率的に働くためには、そもそも「選ぶ仕事・働き方」を見直す必要があります。努力や工夫だけでは限界があるため、環境や契約形態から変えることも、長期的には非常に有効です。
時間で縛られない成果報酬型の案件を選ぶ
時給制や月給制など、時間に応じた報酬の仕事では早く終わらせても報酬は変わらないため、効率化が収入アップに直結しません。
一方で、「1案件いくら」「成果に応じて報酬が決まる」ような仕事であれば、時間を短縮しても報酬は下がらず、むしろ時間単価が上がる構造になります。
たとえば、以下のような働き方が該当します。
- ライター・デザイナーなどの成果物ベースの業務委託
- 営業やマーケティングでの成果報酬型契約
- Web系やIT系のプロジェクト単位の契約
時間よりも成果や価値に対して報酬が支払われるため、自分のペースで働きやすく、時間短縮のメリットが活きやすいのが特徴です。
クライアントや職場の「価値観」も重要(成果重視 or 時間重視?)
どれだけ効率化を意識しても、周囲の価値観が「時間で評価する文化」である場合、かなりのストレスを抱えます。たとえば、以下のような文化の職場です。
- 定時まで仕事がなくても帰れない
- 長時間働く人が評価される
- 残業=頑張っているという扱い
このような職場では効率化のメリットが評価につながらず、むしろ浮いてしまうこともあります。
逆に、「成果が出ていればOK」「時間よりもアウトプットを重視する」といった組織やクライアントであれば、効率的な働き方を積極的に取り入れても認められやすく、心理的にも楽です。
仕事を選ぶときには、業務内容だけでなく、「その会社や人がどんな価値観を持っているか」にも注目しましょう。
副業・業務委託・フリーランスなども視野に
時間の自由度を高めるには、会社員だけにこだわらない働き方も有効です。たとえば以下のような働き方です。
- 副業:会社の収入に加えて別の軸で収入を得ることで、自分の市場価値や可能性を広げることができる。
- 業務委託:会社員より自由度が高く、自分で報酬交渉やスケジュール管理ができる。
- フリーランス:営業や収入管理も自分で行う必要があるが、すべてを自分で決められ、自由度が高い。
これらの働き方は、複数の収入源を持つことにもつながります。収入の安定性という観点でも1社依存よりも安心感があり、精神的にも余裕が持てます。
また、「会社員 or フリーランス」の二択ではなく、ハイブリッドな働き方(本業+副業、本業+業務委託など)も、時間単価を高める現実的な選択肢です。
会社員でも1日6時間労働が可能な理由と条件
会社員の方は「1日6時間労働なんて、自営業やフリーランスじゃないとムリ」と感じるかもしれません。実は会社員でも「1日6時間労働」を実現する道はあります。以下のような制度やポジションを上手く活用すれば実現可能です。
フレックスタイム制・時短勤務を活用する
フレックスタイム制や裁量労働制を採用している会社では、自分で労働時間を調整できる場合があります。
また、育児・介護などの理由で「時短勤務制度」を使いつつ、成果重視で評価されるポジションに就くことも、収入維持の鍵を握ります。
高付加価値の専門職
業務時間よりも成果やアウトプットが評価される職種では、労働時間が短くても収入は維持しやすいです。たとえばエンジニアやマーケター、営業などが該当します。
スキルアップや社内異動でこのような職種を目指すのもひとつの方法です。
会社に頼らず副業で年収を補う
時短勤務にして収入が下がっても、副業で+月5~10万円を確保できれば、トータルで年収はキープ可能です。とくにWebサイトや動画などの自動収入源を持つと、収入が安定しやすくなります。
近年は副業OKの企業も増えてきているので、有効な選択肢のひとつです。
まとめ
1日6時間労働は働き方や仕事の選び方、日々の工夫次第で十分に実現可能なライフスタイルです。集中力の維持、プライベートの充実、健康的な生活リズムなど、6時間労働には多くのメリットがあります。ただし、収入やキャリアへの不安を乗り越えるには戦略的なアプローチが不可欠です。
時間単価を上げるためのスキル構築や、成果報酬型の仕事へのシフト、時間ではなく価値で評価される環境への転換は、その第一歩です。業務効率を高める工夫や、不要な仕事をやらないという選択も、生産性を高めるうえで欠かせません。
これからの時代は、「長く働く」よりも「短く、価値ある成果を出す」働き方が求められます。もし今の働き方に違和感を抱えているなら、まずは小さな改善から始めて、時間の使い方を見直してみることをおすすめします。