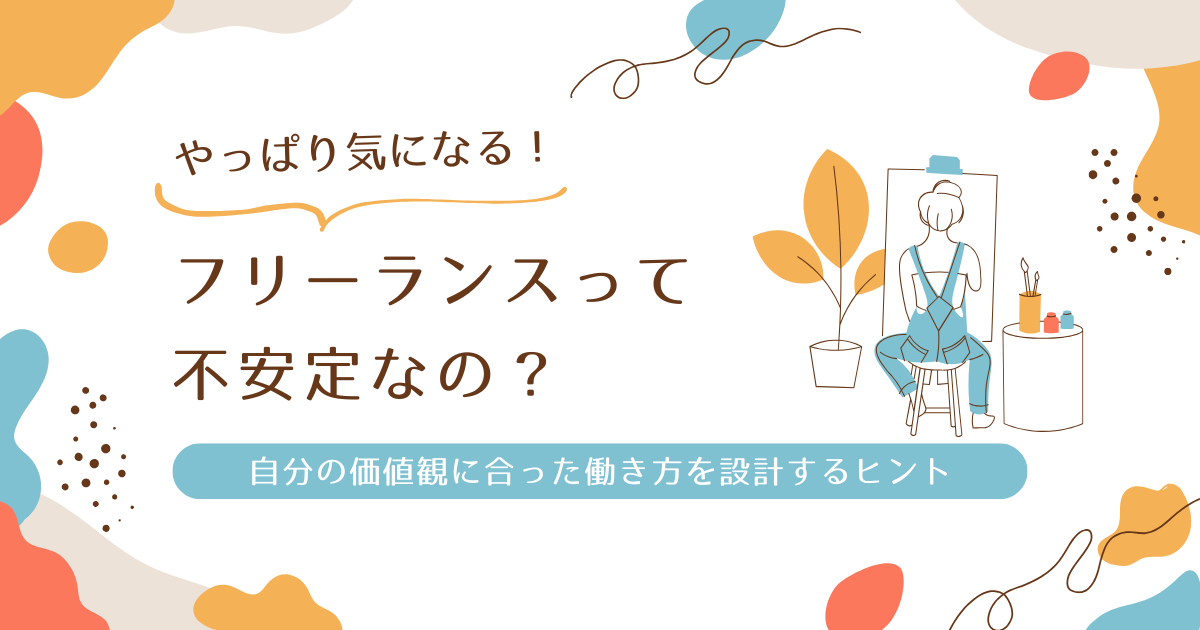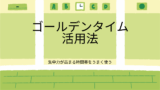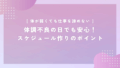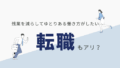「フリーランスって自由でいいよね」と言われることがよくあります。たしかに、働く時間や場所を自分で選べるのは魅力的です。でもその一方で、「いつまで仕事があるんだろう」「来月の収入は大丈夫かな」といった不安を抱えることは多々あります。
私は会社員として10年働いた後、フリーランスとしても10年過ごしてきました。その中で感じた「不安定さの正体」と、そこから抜け出すための工夫について解説します。フリーランスという働き方に興味があるけど不安に感じている方や、フリーランスとして不安定さの壁にぶつかっている方は参考にしてください。
なぜフリーランスは「不安定」と言われるのか?
まずは、多くの人が感じる「フリーランスって不安定だよね」の中身を整理してみましょう。不安定の中身は、大きく以下の4つに分類できます。
- 収入が安定しない
- 仕事が突然なくなる
- 社会保障が弱い
- 孤独・メンタル面の不調
これらはどれも、対策をしないと心身ともに疲弊してしまう要因になり得ます。
収入が安定しない
フリーランスは固定給がないため、収入が月ごとに大きく変動します。クライアントの予算やプロジェクトの状況、季節要因など、さまざまな外部要因で仕事量が変わってしまうためです。そのため、「今月は全然稼げない」「来月の見通しが立たない」といった不安が常につきまといます。
特にフリーランス初期は単価も低く、案件も安定しづらいため、不安に感じる方は多いでしょう。この時期は計画的な家計管理や貯金の重要性が特に高いです。
仕事が突然なくなる
フリーランスとして仕事が軌道に乗ってきても、「ある日突然仕事がなくなる」という事態に直面することがあります。
わたしが今まで突然仕事がなくなったケースとして、クライアント側に発生した以下の理由があります。
- 社内方針の変更で外注をやめて内製化することになった
- コンテンツ戦略の変更でしばらく発注をストップすることになった
- (個人のクライアント)体調不良で事業をやめることになった
会社員の場合、会社の方針変更があっても、仕事が急になくなることはありません。労働基準法で守られているため、解雇されるリスクもかなり低いです。倒産のリスクはありますが、そこまでの状況に陥っていなければ基本的に安定して仕事があります。
しかしフリーランスは雇用契約ではないため、クライアントがある日突然仕事を打ち切りにしても守ってもらえません。いわゆるフリーランス法はできましたが、かなり理不尽な要求や受領拒否などが対象であって、単なる会社の方針変更などによる仕事の減少は回避できません。
参照:公正取引委員会|フリーランスの方のために、新しい法律がスタートします。
また、フリーランスにとって仕事は自分で取りに行くものなので、営業を止めた瞬間に収入が止まる可能性もあります。収入源を1社に依存すると大きなリスクを抱えるため、常に複数のクライアントや案件を持つことがリスクヘッジになります。
社会保障が弱い
会社員であれば、厚生年金や健康保険、雇用保険といった公的なセーフティネットに守られています。
しかしフリーランスになると、これらの多くが自分の責任になります。国民年金は将来の年金額が少なく、病気やケガで働けない期間に保障される制度もありません。そのため、収入の一部を私的年金や民間保険、貯金にまわす「自衛の備え」が必要です。
わたしは社会保険労務士という資格を保有しているのですが、この勉強を通じてさまざまな社会保障について学び、「会社員は本当に恵まれている」ということを知りました。そのため、フリーランスになる際にもっとも不安だったのは、社会保障が弱いという点です。
孤独・メンタルの不調
自由な働き方を選んだつもりが、気づけば誰とも話さない日が続いてしまう……。フリーランスにはよくあることです。仕事の相談相手がいない、成果を共有する人がいない、自己評価が難しいなどの状況は、地味に精神をすり減らしていきます。
また、仕事と生活の区切りが曖昧になりやすいため、自己管理が苦手な人ほど知らないうちにストレスが蓄積してしまう傾向があります。メンタル面のセルフケアや、意識的に人とつながる時間を設けることも重要です。
不安定さを乗り越える5つの具体策
では、こうした「不安定さ」にどう向き合えばよいのでしょうか?10年のフリーランス経験を通じて実践してきた方法の中から、特に重要だと感じた5つを紹介します。
1.スキルや収入源の多様化でリスク分散
フリーランスにとって「収入の柱が1本だけ」というのは非常に危険です。ある分野の市場が縮小したり、主要なクライアントが離れたりした場合、一気に収入が途絶える可能性があります。
しかし1つの分野に依存せず、複数のスキルを持つことで収入源を分散できます。たとえばライティング・デザイン・講座開催などです。
同じ「ライティング」というスキルでも、IT、法律、転職など異なるテーマにわたって専門知識を発揮できるようにすることも大切です。すると、クライアントにとって「相談しやすい・依頼しやすい存在」になり、リピートや紹介につながります。
さらに、クライアントを複数持つことでリスクを分散できます。
2.稼働時間の最適化(少ない時間で最大の成果)
私は現在、1日4時間・週休3日を目安にゆるく働いていますが、それを支えているのは「時間の使い方の最適化」です。
タスク管理や時短ツール、ルーティン化などを活用し、「働く時間は短くても、成果を出す」仕組みを作ることが重要です。長時間働けば成果が出るとは限りません。むしろ、限られた時間の中で最大の効果を出す工夫こそが、フリーランスに必要な力です。
自分が本当に成果を出せる時間帯に集中することも効果的です。
3.固定収入化の工夫
「毎月○万円は確実に入る」という柱が2~3本あるだけで、精神的にも安定し、戦略的な活動にも集中できるようになります。フリーランスでも、ある程度安定して収入を得ることは可能です。
たとえば、定期記事の執筆やSNS運用代行、動画編集など、毎月依頼される仕事は割とあります。永遠に続くわけではないですが、長期のプロジェクトだと数か月単位で定期発注があることも多いです。複数のプロジェクトを掛け持つと、ひとつが終わってもほかのプロジェクトが進行して依頼が途切れることがなくなります。
もちろん、そのためには、仕事の質を上げる努力が欠かせません。クライアントからしてみれば、質の高い成果物が提出されるという信頼があるからこそ、「定期的に依頼しよう」と考えるわけです。
フリーランスになって最初の頃は、単発の仕事をこなすことが多いはずですが、ひとつずつの案件に手を抜かずに質を高めることが大切です。そうしていると信頼関係が構築され、定期案件を発注してもらえるケースが増えてきます。

クライアントワーク以外で、自分でサービスをつくることもリスクヘッジには有効です。たとえばサイトの運営や月1のオンライン相談など、少しでも定期収入を得られるようになると、かなり安定してきます。
4.経費と貯金のコントロール
支出を把握し、必要な生活費を明確にしたうえで、収入が少ない月にも備える貯金習慣を身につけることも重要です。
たとえば生活費に20万円かかる場合、「生活費20万円+ゆとり費5万円=25万円」くらいを目安に決め、月25万円を目標に収入を得ましょう。そのうえで、20万円で暮らせるライフスタイルを構築します。そうするとムリなく貯金もできて生活への不安も減っていきます。
また、フリーランスの場合は収入がいつもより多い月もあります。そのときも気を緩めず、残りは必ず貯金や投資に回す習慣を身につけることが大切です。
さらに年1回の大型出費(税金、保険料など)も見越して年単位の資金計画を立てることで、不安をぐっと減らすことができます。
5.心の安定を保つ習慣づくり
フリーランスは孤独になりやすく、メンタルの安定が仕事のパフォーマンスに直結します。そのため、心の安定を保つ習慣づくりが必要です。
わたしの場合、朝のヨガやストレッチ、趣味の時間など仕事以外の空白時間を意識的に作ることで、心の余裕をキープしています。特に趣味の時間は大切にしていて、読書やお菓子作り、お絵かき、英語の勉強、スポーツ観戦など、好きなことは意識してやるようにしています。
また、基本的に「土曜日は仕事をしない」と決めて、「気付けば毎日仕事をしている」という状況を避けています。
さらに、孤独を感じすぎないように、友人や知人、家族などと会うことも大事です。
まとめ:フリーランスは「設計次第」で安定も実現できる
「フリーランスは不安定だから無理かも」と感じる方も多いと思います。しかし、その不安定さの正体を理解し、対策を講じることで、自分なりの安定は十分に作れます。
わたしは決して高収入ではありませんが、時間を自由に使えて、人間関係のストレスがほぼなく、自分の努力次第で成果につながるこの働き方をとても気に入っています。
大切なのは、他人の理想ではなく、自分の価値観に合った働き方・暮らし方を設計することです。フリーランスが不安定かもと思っている方は、まずは「自分がどんな働き方をしたいのか」を、ぜひじっくりと考えてみてください。