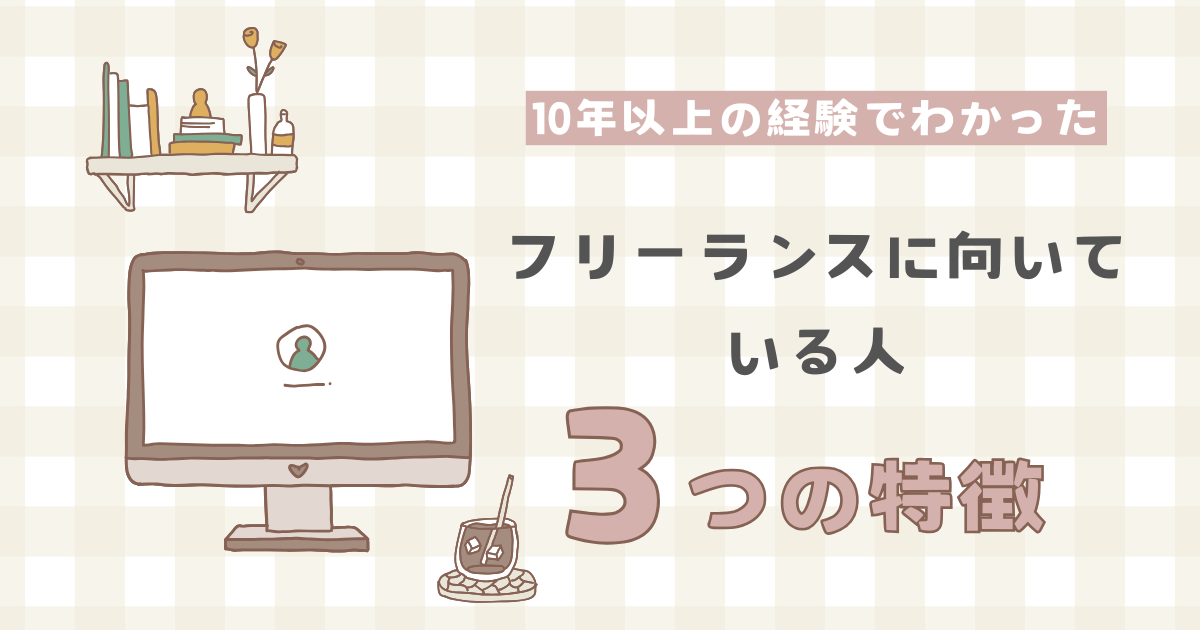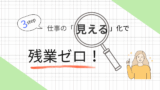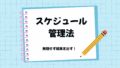「自由な働き方がしたい」「会社員では味わえないやりがいを感じたい」などの思いからフリーランスを目指す人が増えています。しかし、自由と引き換えにすべての責任を背負う働き方には、向き不向きがあるのも事実です。
本記事では、フリーランスに向いている人の特徴を3つに整理しながら、向いていないと感じたときの対処法も紹介します。会社員と副業を組み合わせたハイブリッドな働き方を含めて、自分らしい働き方のヒントを見つけてください。
フリーランスに向いている人の3つの特徴
フリーランスとして安定して活動するには、スキルや経験以上に働き方の適性が重要です。ここでは、フリーランス歴10年以上の筆者が、フリーランスに向いている人の主な特徴を3つ紹介します。
自己管理能力が高い
出社義務がないフリーランスは、時間の使い方がすべて自分次第です。そのためつい夜型生活になったり、納期直前に焦ったりする人もいます。だからこそ、自己管理能力の高い人に向いています。これには、ルーティンを自分で作れる力、タスクを可視化してコツコツ積み上げる力などが含まれます。体調を崩すとそのまま収入減に直結するため、生活リズムや健康維持にも気を配る必要があります。
高い自己管理能力が求められる反面、自分の最適な働き方を自由にデザインできる楽しさがあるのも、フリーランスの魅力です。スケジュール管理から目標管理、健康管理まですべて自己責任ですが、逆に言えば自分の裁量で自由にコントロールできる楽しさがあります。
孤独耐性がある
フリーランスは基本的に1人で作業を進めることが多く、相談相手がいない状況も珍しくありません。チームの雑談や上司からのフィードバックがないことに不安を感じる人は、孤独感に飲まれてしまうこともあるでしょう。そのため、孤独への耐性が高い人に向いています。
1人でも孤独だと不安に感じるのではなく、「集中できる環境」として活用できる人は、作業効率も高まり、安定した成果を出しやすくなります。たとえば、普段から読書や学習、思考の時間を楽しめるタイプのように、孤独を創造性や集中力に変えられる人はフリーランス向きといえるでしょう。
営業力(または発信力)がある
どんなに実力があっても、仕事の依頼がこなければ意味がありません。また、仕事は自動ではきません。そのため、営業力がある人に向いています。
営業と聞くと抵抗を感じるかもしれませんが、「仕事の成果を発信する」「ポートフォリオを整える」「知人に声をかける」といった活動も立派な営業です。苦手意識がある人も、小さな一歩から始めることが大切です。

私も営業は苦手ですが、ニーズがありそうな企業に対し、ポートフォリオを送るという形でアピールし、継続的な仕事をいただいた経験があります。一般的にイメージされる「訪問営業」や「電話営業」のようなことはしなくても、仕事を獲得することは十分に可能です。
フリーランスに向いていない人の特徴とその対処法
次に、フリーランスに向いていない人の特徴を紹介します。しかし、「フリーランスには向いていないかも……」と思っても、すぐに諦める必要はありません。向き不向きを理解したうえで、自分なりの工夫や対策をすることで、フリーランスという働き方を柔軟に取り入れることは可能です。
スケジュール管理が苦手な人
スケジュール管理が苦手な人はフリーランスに向いていません。納期が守れなかった場合には信用にも関わります。たとえば会社員の場合、上司や先輩が声かけしてくれたりチームのメンバーがフォローしてくれたりと、スケジュール管理が苦手でも切り抜ける方法があるかもしれません。しかしフリーランスは1人なので、自分のことは自分で責任をもつ必要があります。
スケジュール管理が苦手な人は、最初は「タスク管理ツールを使う」「1日の予定を朝に書き出す」などの基本的な管理法を徹底しましょう。自分に合う方法を試行錯誤して見つけることが、継続的な改善につながります。
一人で考え込む癖がある人
問題や悩みを抱えたとき、すべてを自分の中で処理しようとすると、思考が煮詰まってしまうことがあります。そのため、一人で考え込む癖がある人には向いていません。
孤独を感じたら、オンラインコミュニティや勉強会に参加する、信頼できる仲間と定期的に会話するなど、人とのつながりを持つ工夫をしましょう。家族や恋人に話を聞いてもらうだけでも構いません。相談できる相手がいるだけで、不安が大きく和らぎます。
すぐに結果を求めすぎる人
すぐに結果を求めすぎるのもフリーランスに不向きな人の特徴です。フリーランスは結果が出るまでに時間がかかるケースも多く、最初は収入が安定しないこともあります。3ヶ月くらいは修業期間と割り切る気持ちや、小さな達成を積み重ねてモチベーションを維持する工夫などが必要です。焦らず地道に取り組む姿勢が、結果につながります。
会社員とフリーランスのハイブリッドという選択肢
フリーランスに興味があるけれど、今すぐ会社員をやめる勇気はないという方も多いはずです。思いつきでフリーランスになっても失敗する可能性が高いので、慎重になるのは正しいです。最初からすべてをフリーランス的な働き方にする必要はありません。会社員としての安定を維持しつつ、副業としてフリーランス的な仕事を取り入れるハイブリッド型という働き方も、有効な選択肢です。
副業解禁の流れを活かす
近年、多くの企業が副業を認めるようになり、週1〜2日だけフリーランスとして活動する人も増えています。このような働き方は、自分のスキルを試しながら少しずつ経験を積むことで、無理なく独立準備ができるのもメリットです。
会社の仕事が土台になる
会社員として得た知識・経験・人脈は、フリーランス活動の大きな財産になります。たとえば、会社で培ったノウハウを活かして社外でコンサルをするなど、すでにある資産を活かせばリスクを抑えて活動を広げることができます。
両方のメリットを享受する
フリーランスだけでは不安定、会社員だけでは窮屈だと考える人にとって、ハイブリッド型はまさに「ちょうどいい働き方」ではないでしょうか。ハイブリッドなら収入・自由・成長のバランスが取りやすく、自分らしいキャリアを築きやすくなります。
フリーランスが合わないと感じたら「ゆる副業」から再スタート
フリーランスに憧れてなったものの、「やっぱりフリーランスは合わなかった」と感じている方もいるでしょう。このとき、完全に諦めるのではなく、ゆるく続けるという選択肢もあります。無理のない範囲で自分のペースに合った働き方を見つけることで、新たな可能性が広がります。
スモールステップで副業を続ける
たとえば、休日やスキマ時間にできる仕事から再スタートしてみるのはよい方法です。イラスト販売、簡単なライティング案件など、負荷が少なく楽しめるものを選んで続けてみましょう。収入よりも「やっていて楽しい」「少しの成果がうれしい」と思えるかどうかを基準にすると、継続しやすくなります。
「ゆる副業」でも経験は積み上がる
たとえ少額でも、自分で稼ぐ経験は自信につながります。過去に失敗したことがあっても、スタイルを変えれば合う形が見つかるかもしれません。重要なのは、どんなスタイルでも続けることです。経験値は確実に自分の資産になります。
働き方の好みを見直すチャンス
合わなかった理由を丁寧に振り返ってみると、「1人作業が辛かった」「収入が不安定すぎた」など、自分にとって大事な価値観が見えてくることがあります。その気づきをもとに、次のステップを考えると、より納得感のある選択ができます。次のステップは、会社員へ戻る、副業として継続する、新たなスキルを習得して再チャレンジするなど、さまざまな選択肢があります。自分はどんな働き方が好きなのかを見直し、今後のキャリアに活かしましょう。
まとめ
フリーランスには、自己管理能力、孤独への耐性、そして営業力(発信力)が求められます。ただし、これらすべてを最初から完璧に備えている必要はありません。大切なのは、自分には何が足りないかを知り、それを補う工夫や仕組みをつくっていくことです。また、もしフリーランスに向いていないと感じたら、会社員とのハイブリッドな働き方や、「ゆる副業」からの再スタートも有効な選択肢です。働き方はひとつではありません。自分の特性やライフスタイルに合わせて、無理のない形で心地よく稼ぐ方法を探していきましょう。