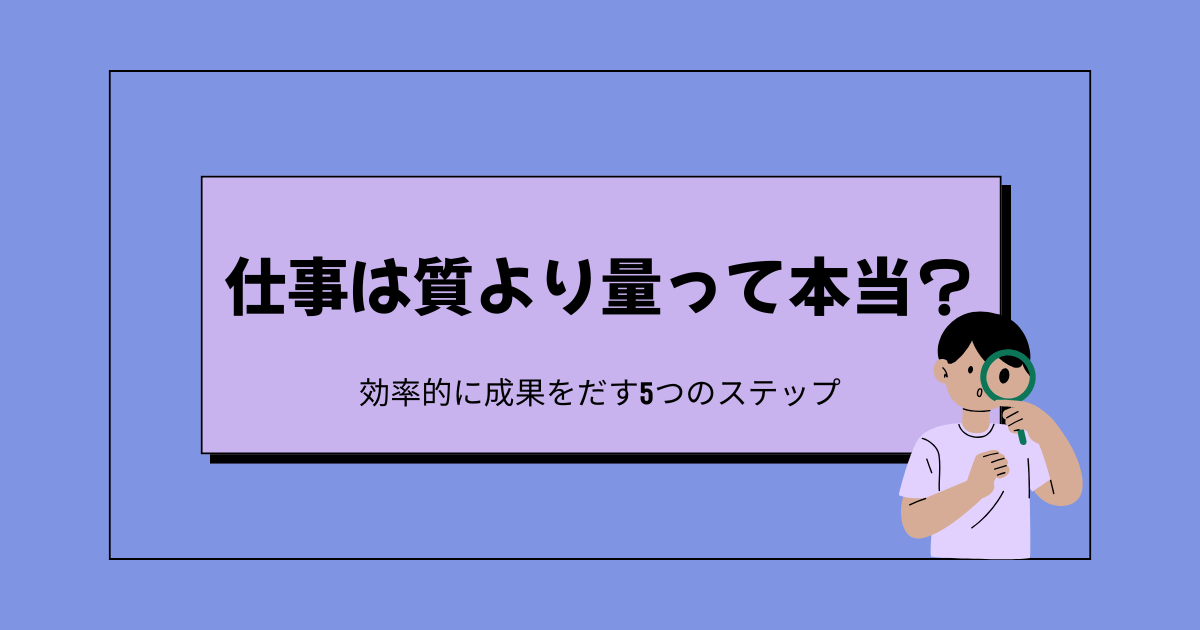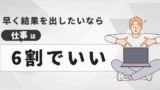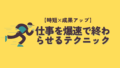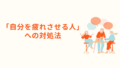「質を高めるにはどうすればいいんだろう?」 「量をこなせば上達するって聞いたけど、本当に?」
仕事や副業などに取り組む中で、この問いにぶつかったことがある方も多いのではないでしょうか。 特に、限られた時間で成果をだしたい人にとって、質と量のどちらを優先すべきかは重要なテーマです。
この記事では、完璧を目指すあまり手が止まってしまう状態から抜け出し、成果につながる行動を継続するための思考法を解説します。
「考えすぎて動けない」ことの落とし穴
仕事をする中で、クオリティを追求するあまり、手が止まり、結局成果がでないという悪循環に陥ることもあります。しかし、この「考えすぎて動けない」状態を突破するためには、まず自分の心構えを見直すことが重要です。
完璧主義は意欲の裏返し
「せっかくやるなら完璧に仕上げたい」という気持ちは、真面目で責任感のある人ほど強く持っています。 しかし、その思いが強すぎると、かえって手が動かなくなることがあります。
- 納得できないから提出できない
- もっといいアイデアがでるまで待ちたい
- フィードバックが怖いから出せない
このような考えは、多くの方がしたことがあるのではないでしょうか。
未完成のアウトプットは改善の第一歩
実は「やってみないとわからない」「出してみないとわからない」ことは想像以上に多いものです。
提出して初めて気づく反応や修正点、ニーズとのズレ……。 アウトプットを通してしか得られない学びが確かに存在します。
だからこそ、まずは未完成でもいいから出してみる。そこから質を磨くステップが始まります。
質を高めたいなら、まずは量をこなそう
「質より量」と聞くと、一見すると矛盾しているように感じるかもしれません。「いやいや、仕事は質がすべてでしょ?」と思う方は多いはずです。
しかし、実は質を高めるためには、まず量をこなすことが不可欠なのです。仕事では最初から完璧を目指してしまうと、逆に行動が遅れてしまったり、成果が上がらなかったりします。

たとえば「自分のサイトを運営する!」と言っているのに、効率的な運営方法のノウハウや優良な記事の書き方を調べるばかりで1文字も書かない人は、一生サイト運営で生計を立てることができません。こういう人って、意外と多くいます。
まずは量をこなし、そこから学びを得ていくという積み重ねこそが、最終的に質を向上させます。
なぜ「質より量」が有効なのか?
まずは量をこなすことが必要なのは、量をこなすことで自然と質が向上するという考え方に基づいています。これを「質量転化の法則」といいます。
質量転化の法則は、量が一定の基準を超えたときに質に転化する、つまり量的な蓄積がある一定の段階を超えると、質的な変化が生じるというものです。ドイツの哲学者ヘーゲルはこの考え方を提唱し、物事が量的に増えていく中で質的な変化が現れることを指摘しました。
仕事においても、最初から完璧なものを作ろうとするよりも、とにかく数をこなしながら、その過程で気づきや改善を積み重ねていくことが重要です。量をこなすことで、次第にその質が上がり、より効率的で質の高い成果をだせるようになります。
このように、初めは量を重視し、それを繰り返すことで、後に質が自ずと向上するというプロセスが重要です。
やみくもに量をこなすのはNG
ここで注意したいのは、「とにかく手を動かせばいい」という誤解です。確かに最初の一歩としてはそれでもよいですが、長期的に見れば、考えながらこなすことが必要です。
たとえば新入社員の中には、上司から「とにかく手を動かせ」と言われて、むやみに作業を繰り返すことがよくあります。毎日同じ内容のレポートを何度も書いたり、メールのテンプレートをただコピペして送信することに時間を費やしたりといったことです。
しかし、こうした意味のない行動を何度繰り返しても、ただ時間を浪費しているだけで、スキルや成果にはほとんどつながりません。
重要なのは、単に数をこなすことではなく、その過程で「振り返り」と「改善」を繰り返すことです。
行動した数=経験値ではなく、「行動→振り返り→改善→また行動」を繰り返すことで、初めて経験値として積み重なります。
振り返りの段階では、自分がどこでつまずいたのか、どこに改善の余地があるのかを明確にします。それを次に活かすことで、質が向上し、仕事の効率化が進みます。
量をこなす行動が「ただの作業」にならない工夫
量をこなすことは重要ですが、それだけでは質は向上しません。以下の工夫を取り入れることで、アウトプットの質を確実に向上させることができます。
1. 毎回1つ新しいことを試す
毎回違ったアプローチや方法を取り入れることで、新たな学びが得られます。たとえば文章を書く際の表現方法を変えてみたり、時間配分を工夫したりするだけでも効果的です。
2. 振り返りと反応をメモ
作業後に簡単な感想や反応をメモして、次回の改善点を見つけます。この振り返りが質を高める第一歩です。
3. 他人のフィードバックを活かす
フィードバックを素直に受け入れ、それを実際の行動に反映させることが成長の鍵を握ります。他人の意見を取り入れることで、視野が広がり質が向上します。
4. 定期的な振り返りを行う
定期的に自分の成果を振り返り、改善点を整理します。これにより、質を持続的に向上させることができます。
5. 失敗から学ぶ
失敗を学びの材料として捉え、改善策を考えます。失敗を分析し次回に活かすことで、質の向上が実現します。
【実践】量をこなしながら質を高めるための5ステップ
実際に量をこなしながらも、効率的に質を向上させるためには、計画的に取り組むことが重要です。ここでは、量をこなしつつ、着実に質を高めていくための実践的な5つのステップをご紹介します。このステップを踏むことで、行動が加速し、改善のサイクルを効果的に回すことができます。
ステップ1.まずは締め切りを決める
まずは締め切りを決め、どんな形でもいいから完成させることを意識しましょう。
仕事をしていると、終わりの見えないタスクや、細かい部分を気にしてしまう場面がよくあります。しかし締め切りを決めておかないと、完璧を目指して仕事が遅れてしまいます。
まずは「今日はこの時間内に○○を終わらせる」と決めてしまいましょう。時間を意識して区切ることで、終わらせるために集中せざるを得なくなり、途中で完璧を求めて止まってしまうことを防げます。
こうしたやり方で、時間がない中でもまずはアウトプットすることが重要です。完成度にこだわらず、とにかく提出できる状態に仕上げましょう。
ステップ2.最初から完璧を目指さない
重要なのは、「60点でOK」と割り切ることです。後で修正すればいいのです。
たとえばプレゼンテーション資料を作成する際、「これで100点満点だ!」と思って何度も修正を加えて時間をかけるよりも、まずは60点程度でいいので一度作成してみましょう。
次回、同じ内容で修正する際に「ここをこうしたらもっと分かりやすくなる」「これを追加すればもっと説得力が増す」といった新たなアイデアが浮かび、質が向上していきます。
完璧を目指すのではなく、次回に向けた改善点を見つけるための一歩と割り切りましょう。
ステップ3.反応を見る
反応があるからこそ、改善点が見えてきます。
自分の成果物が他の人の目に触れることで、初めて気づく点が多くあります。たとえば、報告書を提出したり、会議で発表したりすると、上司や同僚からのフィードバックが得られます。このフィードバックこそ、改善に必要な「気づき」の源です。
自分では完璧だと思った内容も、他の人から見れば異なる意見や視点があるものです。そのため早い段階で周囲に公開し、反応を得ることが大切です。
たとえば、上司に途中段階の報告をしてみて、意見を聞くことが改善への第一歩です。
ステップ4.振り返って、改善点を1つ見つける
完了させたたまま放置しないことが重要です。自分なりの「気づき」を記録しましょう。
たとえば営業報告書を毎週書いている場合、前回と同じ内容でも「この部分をもっと簡潔にまとめたら、より伝わるかもしれない」とか、「次回はこういうデータを加えると、説得力が増すかもしれない」といった改善点が浮かびます。
振り返りは、単なる反省ではなく、今後に活かせる改善点を見つける作業です。振り返った内容をメモに残し、次に同じような作業をするときに意識的に改善点を活かしましょう。
ステップ5.次のアウトプットに、1つだけ改善を反映
仕事で成果をだすためには、小さな改善を積み重ねていくことが重要です。
改善点が見つかれば、それを次回のアウトプットに少しずつ反映させていきます。一つひとつのアウトプットが質を高めるための土台となります。
たとえば月次レポートを提出した際に「次回はグラフの見せ方を変えてみよう」「データの並べ方を工夫して、もっと見やすくしよう」といった小さな改善を加えます。すると、回を重ねるごとにレポートの質がどんどん上がっていきます。小さな変化の積み重ねが大きな成長につながるのです。
質と量、どちらを優先するかではなく「順番」が大事
質と量は、どちらか一方を選ぶものではありません。
- 最初に必要なのは量。
- 量をこなしながら、質を上げていく。
- やみくもな量で終わらせず、改善の意識を持つ。
この順番を意識するだけで、仕事の成果も自己成長も大きく変わってきます。
まとめ
「質を高めなければ」「もっといいものを」と思う気持ちは大切です。 しかし、考えすぎて何も出せないのでは、何も変わりません。まずは手を動かす。出してみる。そして考える。 その繰り返しが、やがて100点を生む土台になります。完璧を目指すより、まず60点を10回出す勇気が、質と成果の両方を引き寄せる第一歩です。