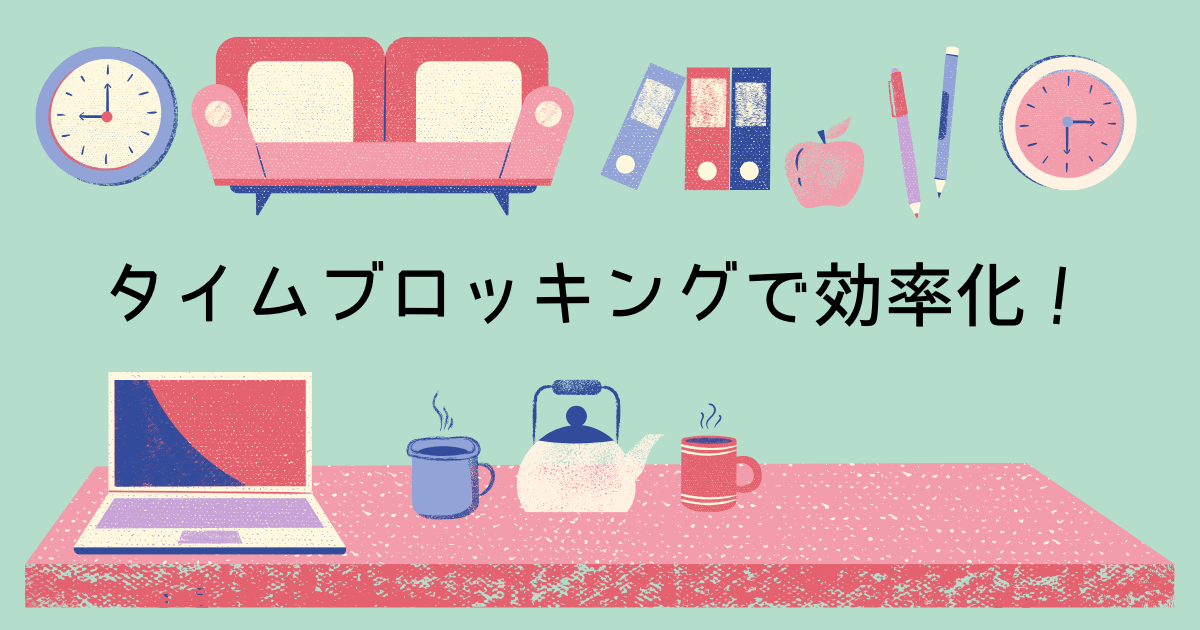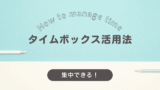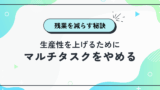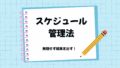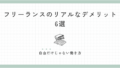「時間が足りない」「いつも時間に追われている」と感じることはありませんか?そんな悩みを解消するためにおすすめなのが、タイムブロッキングという時間管理術です。
タイムブロッキングを使えば、ただ仕事をこなすのではなく、本当に重要なことに集中し、効率的に成果を上げることができます。
この記事では、タイムブロッキングの基本から実践的なコツまで、わかりやすく解説します。忙しい毎日をもっとスマートに、かつストレスフリーに過ごしたい方に適した方法です。
タイムブロッキングとは
タイムブロッキングとは、あらかじめ「この時間はこれをやる」と予定を時間単位でブロックしておくシンプルな時間管理術です。
カレンダー上に「集中作業」「会議」「メール処理」「休憩」などをスケジュールとしてブロックし、時間の使い方を見える化します。
こうすることで、無駄な時間を減らし、集中力を最大限に引き出すことができます。
よく使われるToDoリストとの違いは、「やること」だけではなく「いつやるか」を明確に決めることです。
これにより、「やるべきことはあるのに、気がつけば1日が終わっていた」という事態を防ぎやすくなります。
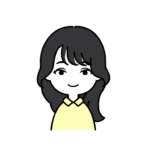
多くのビジネスパーソンが積極的に取り入れている方法ですが、会社員のほかにフリーランス、主婦や学生など、幅広い層が使える汎用性の高い時間術としても注目されています。
タイムブロッキングとタイムボックスの違い
タイムブロッキングとタイムボックスは混同しやすい手法ですが、その使い方や目的に少し違いがあります。
タイムブロッキングは、特定の時間帯に特定のタスクを集中して行う方法です。時間を「ブロック」として区切り、その時間帯に全力で取り組むことを目的としています。
たとえば、「午前9時〜11時はメール処理」「午後1時〜3時は資料作成」など、作業に必要な時間をあらかじめ決めておき、効率よく進めていきます。
一方、タイムボックスは、時間に制限を設けてその枠内で終わらせることを重視する手法です。「あらかじめ決めた時間内でタスクを終わらせる」という意図で行います。
たとえば、「30分以内に会議資料を作成する」「1時間以内にレポートをまとめる」といった具合に時間制限を設定して、時間内にできるだけ多くの作業を終わらせることに焦点を当てます。
- タイムブロッキング:いつ、何をするのかに焦点を当てる
- タイムボックス:時間内でタスクを終わらせることに焦点を当てる
どちらも効率化を目指す手法ですが、その運用方法や意図に少し違いがあるため、状況に応じて使い分けると効果的です。
なぜタイムブロッキングが効率化に効くのか
タイムブロッキングが時間管理に優れている理由は、単に「時間を決めて動く」ということだけではありません。いくつもの心理的・実務的メリットがあります。
ここでは、タイムブロッキングによって得られる代表的な4つの効率化ポイントを解説します。
マルチタスクを防げる
人間の脳は、本来マルチタスクには向いていません。一見、同時進行しているようでも、実際には脳がタスクを高速で切り替えているだけで、集中力や判断力が分散してしまいます。
一方、タイムブロッキングでは、1つの時間枠に1つのタスクしか入れません。
その結果、目の前の仕事に集中しやすくなり、結果的に作業効率が大きく向上します。
「今日は何をしよう?」と迷う時間がなくなる
やるべきタスクはあるのに、どれから手をつけるか迷ってしまい、気づけば時間だけが過ぎていく……。そんな状態を防げるのも、タイムブロッキングの大きなメリットです。
あらかじめ時間ごとにタスクが決まっていることで、「迷う時間」「選ぶエネルギー」を使わずに済みます。
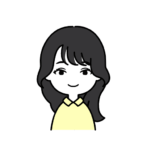
特に朝の時間や疲れているときに効果的です。スムーズな1日のスタートにつながります。
タスクをやり残しても次の予定があるから切り替えやすい
人は完了していないタスクに引っ張られがちです。
しかしタイムブロッキングでは「次に何をするか」がすでに決まっているため、未完了タスクに過剰にとらわれることがありません。
時間に区切りをつけることで、「とりあえず次に進もう」という感覚が自然と身につきます。
これにより、ダラダラと同じ作業に時間をかけすぎることが減り、全体のリズムが整います。
無意識の「空き時間」や「ダラダラ時間」が見えてくる
タイムブロッキングを取り入れると、自分の時間の使い方が見える化されます。
何も予定を入れていなかった時間帯に、なんとなくSNSを見たり、目的のないネットサーフィンをしたりしていたことに気づく人も多いはずです。
この隠れたムダ時間を発見し、意図をもって使い直すことで、「時間がない」と感じていた毎日にも、実は余白があると実感できるようになります。
1日のタイムブロッキング例(タイプ別)
タイムブロッキングの理屈はわかるけど、どうやって実践するのかイメージが湧かないという人も多いかもしれません。ここでは、タイムブロッキングを活用した「とある1日」のスケジュール例をご紹介します。
会社員の一例(在宅ワーク)
会社員の場合、勤務時間がある程度決まっているため、その枠の中でタスクをブロック化するのが基本です。
在宅勤務が増えた今、自己管理の重要性が高まっているので、タイムブロッキングは特に効果を発揮します。
例:在宅勤務の1日スケジュール
- 8:00〜9:00 朝の準備・朝食・メールチェック
- 9:00〜11:00 資料作成・タスク処理
- 11:00〜12:00 会議・打ち合わせ
- 12:00〜13:00 昼休憩
- 13:00〜15:00 企画業務・集中作業
- 15:00〜16:00 報告まとめ・情報収集
- 16:00〜17:00 明日の準備・ゆるめのタスク
- 17:00以降 退勤・オフタイム
フリーランスの一例
フリーランスは時間の自由度が高いぶん、自分で時間を区切らなければ、だらだらと働いてしまうこともあります。
あらかじめ、この時間は何に使うかを決めておくことで、効率的に働けるようになります。
例:フリーランスの1日スケジュール
- 7:00〜8:00 起床・朝食・散歩
- 8:00〜10:00 作業時間(デザインやライティングなど)
- 10:00〜11:00 営業・メール返信・見積もり作成など
- 11:00〜12:00 SNS・ブログ更新・情報収集
- 12:00〜13:00 昼食・休憩
- 13:00〜15:00 クライアント対応・Zoom打ち合わせ
- 15:00〜16:00 資料整理・経理処理
- 16:00〜17:00 インプットタイム(読書・学習)
- 17:00以降 自由時間・外出・趣味など
自由時間・プライベートのブロックも大事
タイムブロッキングは仕事の効率化だけでなく、プライベート時間の充実にも効果的です。
「何もしない時間」や「ゆっくりする時間」も予定に組み込むことで、罪悪感なく休むことができます。
例:平日の夜や休日のタイムブロック
- 17:00〜18:00 夕食の準備・家事
- 18:00〜19:30 家族との時間・食事
- 19:30〜20:30 入浴・リラックス
- 20:30〜22:00 趣味・読書・ドラマなど
- 22:00〜23:00 明日の準備・就寝前のストレッチ
自由時間に何をするかを事前に決めておくと、「なんとなくスマホをいじって終わる」時間が減り、生活の満足度が高まります。
タイムブロッキングを実践する際のコツと注意点
タイムブロッキングはシンプルな手法ですが、継続して効果を出すためには、いくつかのコツと注意点があります。うまく取り入れることで、ストレスなく、時間の使い方が上手な自分に近づけます。
最初から完璧を目指さない(ズレてもOK)
タイムブロッキングの予定は、あくまで予定です。実際にはタスクが長引いたり、急な対応が入ることもあります。
予定が少しズレても落ち込まず、「今日はここまでできた」と柔軟に捉えることが大切です。
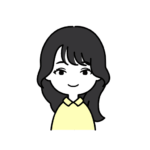
完璧を目指しすぎると続かなくなるので、最初は「おおまかにブロックしてみる」くらいの感覚でOKです。
休憩や予備枠もブロックに入れる
タイムブロッキングというと、すべての時間を仕事で埋めがちですが、それでは逆に疲弊します。
意識的に休憩や予備時間もスケジュールに組み込むことが、継続のコツです。
特に、移動やトラブルなど予測できない時間に対応できるバッファ(余白)を入れておくと、スケジュールが多少ズレても安心感があります。
タスクの粒度をそろえておくと組み立てやすい
あらかじめ粒度をある程度そろえておくと、スケジューリングがしやすくなります。
「粒度」とは、タスクをどれくらい細かく分けるかという「細かさのレベル」のことです。
「1時間でやるタスク」と「5分で終わるタスク」が混在していると、時間ブロックを組むときに混乱しがちです。
粒度の判断として、たとえば「資料作成」は2時間、「メール返信」は30分など、大まかな所要時間の見積もりをしておくのがおすすめです。
タイムブロッキングを習慣化するために
タイムブロッキングは一度やって終わりのテクニックではなく、続けることで効果がじわじわと表れてくる習慣です。毎日使い続けるためには、始めやすさ・見直しやすさ・継続しやすさの3つがポイントです。
ここでは、習慣化のための具体的な工夫をご紹介します。
まずは1日だけ試してみる
最初から「毎日やるぞ!」と意気込まず、まずは1日だけ試してみることが習慣化の第一歩です。
ブロックした通りに動けたか、何がやりにくかったかを振り返るだけでも構いません。
1日だけでも「やることが明確で楽だった」「意外と集中できた」といった手ごたえを得られるはずです。
毎朝5分で見直す/週に1回リセットタイムを設ける
タイムブロッキングは一度作って終わりではなく、こまめな見直しが重要です。
毎朝5分程度、当日のスケジュールを見直すことで、現実とズレない予定が組めます。
また、週末などにリセットタイム(1週間の振り返り&来週の予定づくり)を設けておくと、習慣として定着しやすくなります。
手帳派・アプリ派、どちらでもOK。自分に合う形を探す
「タイムブロッキング=デジタル」と思われがちですが、紙の手帳で管理するのでもまったく問題ありません。
色分けして見やすくしたり、スキマにメモを書いたり、自分のスタイルに合った方法を選ぶことが大切です。
反対に、スマホ通知でリズムを整えたい人には、Googleカレンダーなどのアプリが便利です。
どちらにしても自分が使っていて心地よいと感じるツールを選びましょう。
予定どおりにできなかった自分を責めない
思った通りに進まなかった日も、当然あります。
そんなとき、「私は計画通りにできない人間だ……」と自分を責めると、タイムブロッキング自体が苦痛になってしまいます。
ズレたら調整する、できなかったら翌日に回す。 それくらいの柔軟さが、結果的に継続につながります。
「完璧じゃなくてもOK」というマインドで取り組むのが、習慣化の最大のコツです。
まとめ
タイムブロッキングは、効率的な時間管理を実現するための強力なツールです。最初は少しの工夫と柔軟な調整が必要ですが、実践を重ねることで、驚くほど生活や仕事の質が向上します。
ポイントは「完璧を目指さないこと」と「無理なく続けること」です。予定通りにいかないこともありますが、それが続けられない理由にはなりません。むしろ、時間をしっかりと管理することで、自由時間や自己成長の時間が確保できるようになります。
タイムブロッキングを取り入れることで、時間を上手に使えるようになり、労働時間を減らすことが可能です。ぜひ試してみてください。