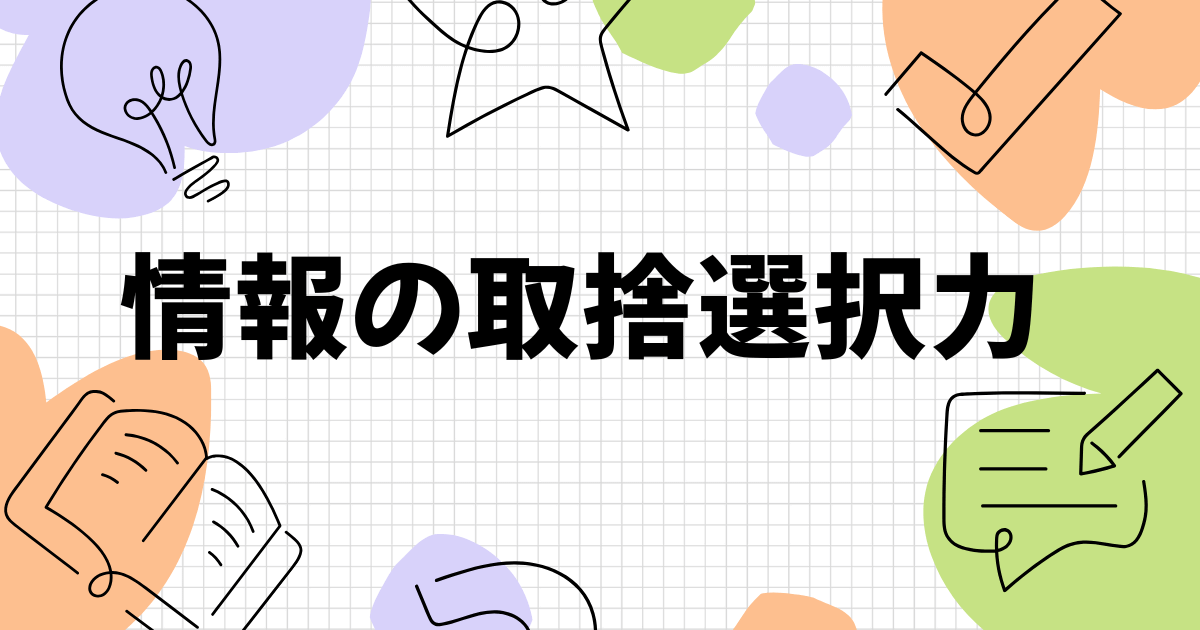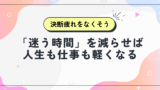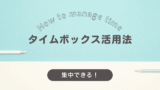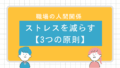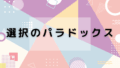スマホやPCを開けば、SNS・ニュース・動画・ブログなど、情報があふれています。
「便利なはずなのに、なぜか疲れる」「どれが本当に自分に必要なのか」がわからず、気づけば時間だけが過ぎている——こんな感覚に覚えがある方は多いのではないでしょうか。
本記事では、「情報を取捨選択する力」をテーマに、情報を選ぶための3つの判断軸と、実践的な情報選別ルールを紹介します。
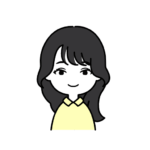
情報に振り回されず、自分にとって本当に必要な行動を選び取る力を手に入れましょう。
なぜ今「情報を取捨選択する力」が必要なのか
情報が溢れる時代、必要なのは多くの情報を持っていることではなく、必要な情報を選べる力です。
仕事も生活も効率よくこなすためには、情報の波に飲まれず、冷静に使える情報を選び取るスキルが欠かせません。
この章では、なぜ今、情報を取捨選択する力が求められているのかを解説します。
情報が多すぎる時代、「全部読む」は非効率
ネットやSNSを開けば、仕事術や健康法、お金の知識など、あらゆる情報が次々に流れてきます。便利なようでいて、すべてをキャッチしようとすると、かえって情報に疲弊してしまうのが現代の課題です。
すべてを吸収しようとすることは、結局何も使えない状態を生んでしまいます。
また、情報には質の差があり、有益なものとノイズが混在しています。無差別に取り入れることで、本当に価値ある情報が埋もれてしまうリスクもあります。
効率よく情報を扱うには、まず選ばない勇気を持つことが大切です。
仕事時間が限られている人ほど選ぶ力が必要
子育て中の人や時短勤務の人、副業・複業をしている人など、限られた時間で成果を出したい人こそ、情報の取捨選択は不可欠です。
「今、何を知るべきか」「何を後回しにするか」を判断できれば、少ない時間でも最大限の効果を出すことが可能です。
限られたリソースをどこに投下するかで、成果の差が生まれます。
すぐに行動に移せる情報かどうか、その判断スピードが速い人ほど、時間あたりの生産性も高いです。
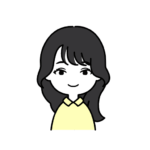
情報の「量より質」を重視することで、無理なく成果を最大化できます。
情報を絞ることで判断力・行動力が上がる
情報を絞ると、迷いが減り、行動スピードが上がります。あれこれ悩んで結局行動できない、という事態も防げます。
つまり、情報を選ぶことは決断力を高め、実行力につながるのです。
判断や行動に一貫性が出てくるため、成果の再現性も高まります。一貫した基準で行動を積み重ねることで、「うまくいった理由」と「改善すべき点」が明確になり、次回以降にも同じ成功パターンを活かしやすくなるためです。
余計な選択肢を減らすことは、本当に大切なことに集中できる環境づくりにもなります。情報を絞ることで、注意力やエネルギーが分散せず、目的達成に近づきます。
情報を選べない人が陥る3つの落とし穴
情報選びがうまくできないことは、気づかぬうちに生活や仕事の質の低下を招きます。以下では、情報を選べないとどうなるのか、よくある3つのケースを解説します。
SNSや無料情報に振り回される生活に
SNSで話題のノウハウ、YouTubeでおすすめされたハウツーなど、目についた情報を次々に追っていると、自分のペースが崩れてしまいがちです。
「自分にとって本当に必要な情報なのか?」の軸を持たないと、情報の洪水に流されてしまいます。
具体的には、やることが増えすぎて優先順位がつけられない、情報に振り回されて疲弊する、他人の成功体験に影響されて自分の軸を見失うといったことが起こります。
無料で簡単に手に入る情報ほど、断片的であったり、文脈が不足していたりすることもあります。
また、情報の鮮度や信頼性を確認せずに鵜呑みにしてしまうと、逆に遠回りになることもあるはずです。
選ぶ力がなければ、情報に支配される受け身の生活になってしまいます。
無駄に学び続けて実行に移せない
今はたくさんの情報にアクセスできるため、手軽にさまざまな学びを得ることができます。学ぶことは素晴らしいですが、学びのための学びに終始してしまうのは危険なことでもあります。
次々と新しい情報を探してばかりで、実際には何も行動に移せていない、そんな悪循環に陥ることもあるでしょう。
知識が増えても、行動に移さなければ成果にはつながりません。
ノウハウコレクターになってしまうと、自信を失いやすくなり、自己肯定感も下がりがちです。
「あれもこれも」と焦ってしまう
「このままでいいのかな?」「もっとよい方法があるんじゃない?」という思考が常に頭を占めると、精神的にも疲れます。選択肢が多すぎることは、不安や焦りのもとになります。
情報が増えると選択肢も増えますが、それが決断疲れを引き起こします。
結果として、何も決められず、目の前の課題にも集中できなくなってしまいます。
情報を取捨選択するための3つの軸
情報をうまく選ぶためには、明確な判断基準を持つことが大切です。ここでは、情報を取捨選択するための3つの軸を解説します。
目的基準で見る:「今の自分に必要か?」
「いつか役立つかも」よりも、「今必要かどうか」で判断するほうが、行動につながります。
情報の価値はタイミングによって変わります。過去には必要だったものでも、今は不要なこともありますし、その逆もあります。
未来の自分ではなく、今の自分に軸を合わせることで、ブレない判断ができます。
それでも判断に迷うときは、無理に即決せず、一度時間を置くこともおすすめです。
たとえば一晩寝かせてみることで、感情的な判断や焦りを避け、冷静に必要性を見極めやすくなります。時間を置くことで、自分にとって本当に大切な情報が自然と浮かび上がってくることも多いです。
時間対効果で測る:「30分でどれだけ役立つか?」
1時間かけて得られる情報と、5分で得られる情報の価値は同じではありません。
「この情報を得るのに、どれくらいの時間をかけるべきか?」という視点を持つと、効率よく情報を扱えるようになります。
意識したいのは、時間対効果です。
たとえば、ある社内向けの資料に入れる業界動向の数字を探す場合、公式な調査レポートを1時間かけて読み込むよりも、信頼できるニュースサイトで要点だけを5分で拾うほうが目的に対して十分なことがあります。
反対に、戦略立案や意思決定に関わる重要なテーマなら、1時間以上かけて複数の視点から深掘りする価値があります。
このように、情報そのものの価値だけでなく「その情報を得るためにかける時間が見合っているか?」という視点を持つことで、効率よく、かつ的確に情報を扱えるようになります。
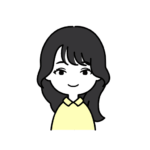
学びや情報収集にかける時間は有限です。短時間で得られる成果の大きさを意識することで、自然と高密度な情報にアクセスする癖がつきます。
一次情報を優先する:経験者・現場の声・公式情報
一次情報の重要性はあらゆる場所で指摘されています。しかし、それでもなお、一次情報を無視してしまう人が多くいます。
情報に振り回される人の多くは、一次情報にアクセスせず、「それ以外」の情報に右往左往しています。
一次情報を優先するというのは、たとえば個人のSNSや要約サイトで見た情報よりも、「現場にいる人」「公式な発信者」からの情報を優先することです。
政府や各省庁のポータルサイト、法律条文、自社情報を発信している企業の公式サイトなどが該当します。
特に法律や制度のように正確さが求められる分野では一次情報の確認が不可欠です。「出どころはどこか?」を意識することで、情報の質を大きく向上させることができます。
一方、情報には「誰かから聞いた情報」「どこかのブログからの引用」「取材していないニュースサイト」などの二次情報もあります。これらの間接的な情報はどうしても主観や誤解が入りやすく、事実と異なる場合も多いため、取り扱いには注意が必要です。
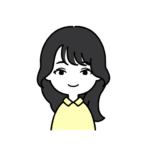
有識者の解説や研究者のまとめなど質の高い二次情報もありますが、情報に振り回されがちな人は「一次情報以外はスルーする」くらいの気持ちでいるのがおすすめです。
今日からできる「情報選別力」の鍛え方
ここからは、情報の取捨選択力を日常の中で育てていくための、具体的なテクニックを紹介します。一気に完璧を目指さず、できることから始めていきましょう。
インプット時間に上限を設ける
インターネットがある現代では、情報収集を始めると際限なく時間を使ってしまいます。
そこで「情報収集は1日30分まで」など、あらかじめ時間を決めておくと、ダラダラと情報を追い続けることがなくなります。
また、余った時間をアウトプットや行動に回せるようになり、バランスのよい情報活用につながります。
ついついネットサーフィンをしてしまう人などは、タイマーを活用するのもおすすめです。時間制限を設けることで、本当に必要な情報だけを選ぶ意識が自然と働くようになります。
情報源を5つ以内に絞る
情報は無限に存在しますが、すべてをキャッチしようとすると時間ばかりが過ぎてしまい、本当に重要な情報に集中できなくなります。
そこで信頼できるメディアや配信者を5つ程度に絞ることで、情報の質と深さが安定します。前述した一次情報だけに絞るのもよい選択肢です。
情報源を限定することで、情報収集の効率が格段に上がります。
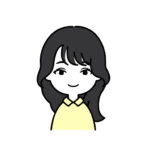
自分にとって価値のある情報に絞り込み、無理に幅広く追いかけることをやめることで、心の余裕も生まれ、選択の質も高まります。
「見た→メモ→使う」を習慣化する
情報の取捨選択力を高めるためには、知識を行動に結びつける意識が欠かせません。
情報は使ってこそ価値があるものです。ただ見るだけでは、その情報が本当に有益だったのか判断しづらく、記憶にも残りません。
見た情報をメモに取り、それを実際に使ってみる・行動に活かすことで、「役に立った情報」と「そうでなかった情報」の違いが実感としてわかるようになります。
この繰り返しによって、自分にとって価値ある情報のパターンが見えてきて、自然と取捨選択の精度が上がっていきます。
また、使う前提でインプットするようになるため、最初から目的意識を持って情報を選べるようになります。
メモの形式はノートでもアプリでもOKですが、ポイントは「すぐに振り返れる形」にすることです。使ってみて効果を実感できた情報は、自分の中で生きた知識として定着していきます。
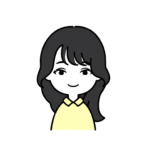
情報をただ「知っている」だけで、実際にそれを使いこなせるわけではありません。「知ってる=できる」ではない。これを強く意識することが重要です。
まとめ
情報を取捨選択する力は、今の時代を効率的に、心地よく生きるための必須スキルです。
そもそも全部を知ることは、どんな天才にもできません。それよりも、必要なものを選べる自分になることのほうが、よほど価値があります。
また、どんなに多くの情報を集めても、それを活かして実際に動かなければ意味がありません。そのため、情報収集に時間をかけすぎず、得た知識をすぐに実践に移す意識を持つことが大切です。
情報選別ルール10箇条
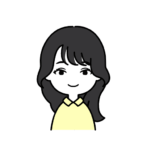
最後に、日常で使える情報選別のルールを10箇条にまとめました。
迷ったときはここに立ち返ってみてください。
- 「今の自分に必要か?」で判断
- 情報収集の時間に制限を設ける
- 情報源は5つ以内に絞る
- SNSの情報はすぐ鵜呑みにしない
- 一次情報を優先する
- 見たらメモ、メモしたら使う
- 「知ってる=できる」ではないと意識する
- すべてを追わなくていいと割り切る
- 迷ったら一晩置く
- 情報より「行動」に重きを置く