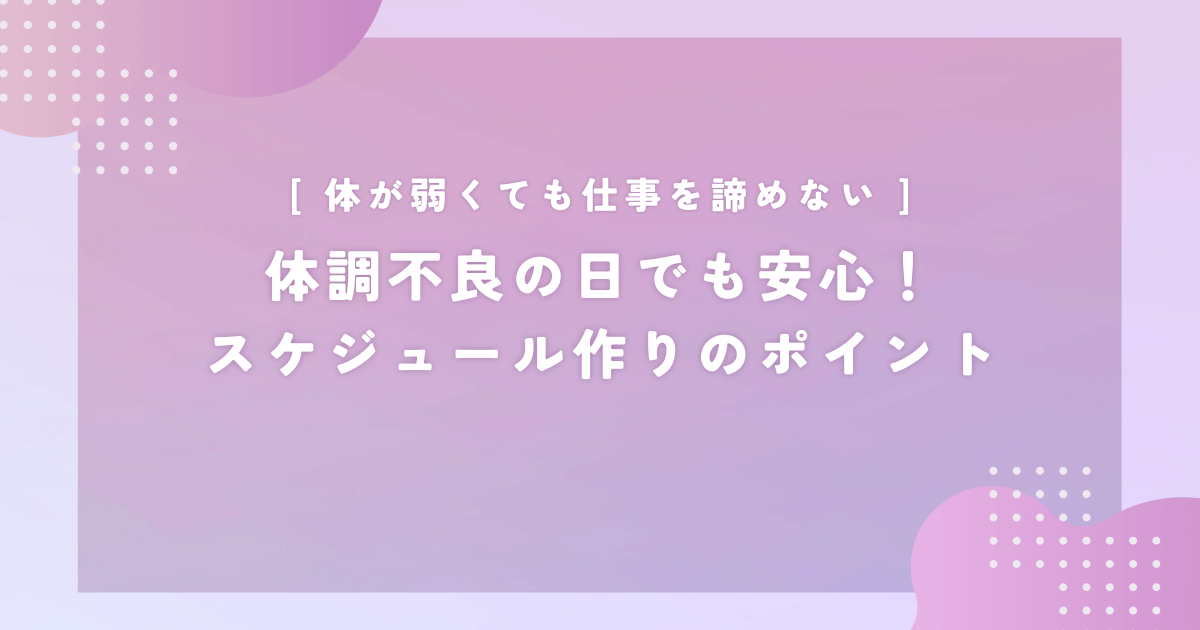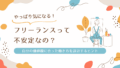体質的に月経痛が重い方や基礎疾患がある方など、「体調不良の日が必ずくる」という方は一定数存在します。そうした日が仕事に影響を及ぼすことに不安を感じている方や、体調不良で仕事を休みがちという方は多いのではないでしょうか。この記事では、そんな「体調不良の日」を考慮した仕事のスケジュール立てのコツを解説します。
毎月必ずくる「体調不良の日」
私も月経痛が非常に重く、その影響で月の半分くらいは体調が超悪い・悪いという状況です。「体調不良の日が必ずある」ことは、私がフリーランスという働き方を選んだ理由のひとつでもあります。
以前は会社員として働いていましたが、「休みたいときに休めない」「仕事中に体調が優れずパフォーマンスを発揮できない」「大量出血でスカートが汚れてしまう」といった困難に直面していました。これが本当に大変だったのです。
フリーランスになってからは、自分の裁量でスケジュールを決められるため、体調不良でも仕事を休みやすい環境になりました。しかし、フリーランスであっても、体調不良の日が必ずくることがわかっている場合、仕事のスケジュールには特別な工夫が必要です。
フリーランスである私は、スケジュールをぎゅうぎゅうに詰めることもできますが、それだと体調が悪い日に無理をして働かざるを得ません。その結果、クライアントに迷惑をかけてしまう可能性があります。だからこそ、余裕を持ったスケジュールを立てることがとても重要だと感じています。
次の章からは、体調不良の日があっても安心して休むための、スケジュール作りのポイントを解説します。
ポイント1.毎月の仕事量を80%程度に抑える
体調が悪くなる可能性のある日を考慮し、毎月の仕事量を80%程度の余裕をもって設定します。具体的には、スケジュールを組む際に、常に数日の「予備日」を確保しておくことで、体調が悪くなった際でも調整しやすくなります。
では、その予備日はどうやって設定すればよいのでしょうか?
1ヶ月の労働可能時間の80%を計算する
まず、1ヶ月の労働可能時間を見積もります。このときは、体調不良日は考慮せず、単純に仕事に費やしたい時間を算出します。たとえば、月20日労働×1日4時間の働き方が理想の場合、80時間が1ヶ月の労働可能時間です。
次に、労働可能時間の80%を目安に、仕事時間を割り当てます。80時間の80%なので、64時間ですね。月20日働くなら、1日3.2時間、1週間16時間です。80時間でスケジュールを立てるのではなく、最初から64時間を前提にスケジュールを組んでいくわけです。そして、残りの16時間(80時間-64時間)、つまり4日分を予備日として設定します。
こうして仕事のスケジュールを立てていきますが、方法はふたつあります。
方法①労働可能時間の80%になるように仕事を計画する
仕事のタスクごとに時間を見積もり、合計が64時間以内になるように仕事を計画します。
まずはタスクをリストアップします。次に、各タスクにかかる時間を見積もりましょう。最後に、64時間を超えないようにタスクを配置してスケジュールを組んでいきます。
方法②その労働時間での最低時給を算出する
各タスクにかかる時間は変動が激しく算出が難しい場合、時給ベースで考えます。
たとえば生活するのに最低でも20万円が必要な場合、64時間働く場合に必要な時給は3,125円です(20万円÷64時間)。最低時給の3,125円を目指して効率よく働けば、64時間働いた時点で月に必要な20万円に到達できます。
ポイント2.タスクには優先順位をつけることが重要
労働可能時間の80%を目安にスケジュールを組むと、必然的に稼働時間が限られます。そのため、常にタスクの優先順位をつけ、重要なタスクから取り組むようにします。
スケジュールを組む際には最も重要なタスクを先に組み込み、優先度が低いタスクは余裕があれば取り組むようにしましょう。これにより、必要以上に仕事を抱えないようにできます。
また、タスクの優先順位を設定しておくことで、体調が悪くなったときにどのタスクを後回しにしてもよいかを把握できます。体調不良の日には、重要度の低いタスクをやる必要はないので、延期する柔軟性をもつとよいです。
ポイント3.「体調不良の日」を予測して休養日を設定する
月経周期や特定の時期に体調が悪くなりがちな場合、あらかじめその傾向を把握してスケジュールに反映させることが重要です。
毎月決まった時期に休養日を設定しておくと、体調不良があっても慌てずに休めます。たとえば月経周期の傾向から月末に体調を崩しやすい場合、月末は特にゆとりをもたせたスケジュールにしておきます。

会社員の方で仕事の休みを取るのが難しい場合は、「家事の休養日」「プライベートの予定を入れずに体を休める日」などと設定しておくだけでも全然違います。
ポイント4.体調がよいときに前倒しで進める
体調不良の日に仕事をしていると、どうしてもクオリティが落ちる可能性があるため、体調のよいときにできるだけ仕事を進めるようにします。余裕があるときにタスクを進めることでクオリティを保ちつつ、急な体調不良になっても早退するなど対応しやすくなります。
クライアント業務が多い方は、早めにクライアントとのやり取りや納期調整を行い、余裕をもたせるようにしましょう。余裕のある締め切りにすることで、体調が悪い日でもプレッシャーを感じにくくなります。
ただし、すべて思うように前倒しすることは難しいはずなので、できる範囲で進めておくくらいの気持ちでやりましょう。
ポイント5.仕事の種類を分ける
体調不良の日に高い集中力を保つのは至難の業です。そのため、体調がよくない日でもできる軽作業やリサーチなど、集中力が必要ないタスクをリストアップしておきましょう。体調不良になってから考えても思い浮かばないので、書いておくことが大切です。
こうすれば、完全に休めないときでも無理なく進められる仕事が用意できます。仕事自体はしているので、休むと罪悪感を感じやすいという方にもおすすめです。
ポイント6.ヘルスケアのルーチンを組み込む
自己努力ではなかなか改善が難しい体調不良であっても、体調不良になる可能性を少しでも抑えるための努力は必要です。たとえば基礎疾患があって体が弱いのに、暴飲暴食や夜更かしを繰り返していれば、さらに体調は悪化するでしょう。
そのため日々のスケジュールには、体調を整える健康的な生活習慣を組み込むことも大切です。たとえば朝起きたときや休憩時間にはストレッチや軽い運動をするといったことです。
適度な運動、バランスの取れた食事、十分な睡眠など、体調管理を意識することで体調不良の頻度を減らすことができます。

体が弱いからといって諦めるのではなく、少しでも元気に過ごすための努力は必要です!
まとめ
スケジュールを完璧に立てたとしても、体調不良の日がきてしまえば一気に予定が狂ってしまいます。そのため、「体調不良の日は必ずくる」と想定し、事前にスケジュールに組み込んでおくことが大切です。また、日頃からタスクの優先順位を決めておくと、体調不良の日でも対応しやすくなります。
「体が弱いけど仕事は続けたい」「体調不良になりやすく仕事がうまくいかない」といった悩みをもっている方は、仕事を辞めるという選択肢を選びがちです。しかし、仕事を完全に辞めることはリスクが多いため、できるだけ続けられる方法を模索することをおすすめします。