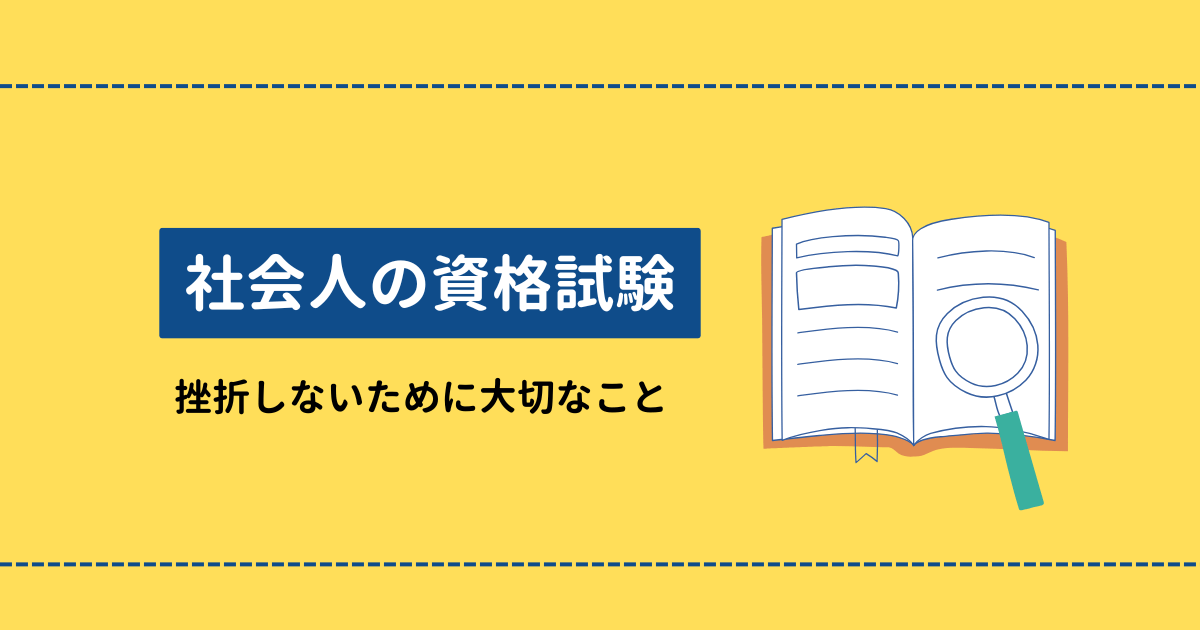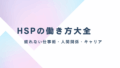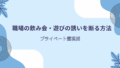リスキリングという言葉が浸透し、資格取得に挑戦したい方は多くいるでしょう。しかし実際には、資格の勉強の途中で挫折してしまう人が7割以上とも言われています。
実は、社会人が挫折するかしないかは、勉強を始める前に決まっています。一体どういうことなのでしょうか?
筆者は、会社員時代に簿記や年金アドバイザー、FP、秘書検定などいろいろな資格を取得しました。合格率6~7%の難関資格、社会保険労務士にも合格しています。
この経験から、きっと皆さんの役に立つアドバイスを提供できると思います。
本記事では、社会人が資格試験で挫折する理由や挫折しないための方法を、わたし自身の経験をもとに解説します。
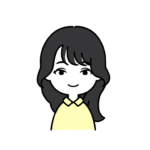
この記事はこんな方におすすめです。
- 資格取得に挑戦しようとしているが、勉強を続けられるか不安な方
- 難関資格に挑戦してみたいが、仕事や家庭との両立に悩んでいる方
- これまで資格勉強を始めても途中で挫折してしまった経験がある方
社会人の資格挑戦と挫折の現実
社会人の多くは、キャリアアップやスキル向上、将来の選択肢を広げるために資格取得に挑戦します。ある調査によると、社会人の約4分の1が資格取得に取り組んでいると言われています。
しかし、現実は甘くありません。多くの社会人は、仕事や家庭の忙しさに追われ、思うように勉強時間を確保できず、途中で挫折してしまうのです。
実際には、資格に挑戦する人の7割以上が、何らかの形で途中で勉強をやめたり、受験に至らなかったりしています。
そもそも試験を受けていない人も多いため正確なデータはないものと思われますが、わたしの肌感覚としても「せっかくスクール代を払っても、3~4割くらいは受験前に諦める」ような気がします。
わたしは社会保険労務士を資格の大原に通って取得しましたが、最初は超満員だった講座の教室が、スクール開始から1ヶ月、2ヶ月と経つうちにどんどん人がいなくなっていったのをよく覚えています。
この記事でいう挫折の定義
「資格試験に挫折する」と言ってもさまざまなパターンがあると思います。結果的に「試験に合格できなかった」パターンとしては、大きく以下の3つがあります。
- 勉強は最後までしっかり取り組んだけれど、難関試験がゆえに合格に至らなかったパターン
- 勉強を途中でやめてしまい、受験自体をしなかったパターン
- 受験はしたものの、勉強時間が足りずに合格ラインにまったく届いておらず、記念受験のような形になってしまったパターン
わたしがこの記事でいう「挫折」は、「2」または「3」のパターンを指します。このようなケースこそ、社会人の資格挑戦で最も避けたい「挫折」です。
試験は一発勝負です。特に合格率一桁台の難関試験は、年1回しか試験がないことが多く、どれだけ頑張っても合格できないことがあります。そのため、しっかり勉強を頑張ったけれど不合格だったことは、挫折と言う必要はありません。挑戦した証であり、努力の結果です。
もっとも、合格するための勉強方法がずれている可能性はあります。合格を目指すなら、きちんと合格指導ができる講師や専門スクールに相談して、方向性を修正してください。自分のやり方の誤りを素直に受け入れ、軌道修正することは大切です。
したがってこの記事では、その試験に合格する方法ではなく、しっかり準備をして本気で試験に挑戦する(勝負できる状態で受験する)ためにはどうすればいいのかについてお伝えします。
社会人が資格試験で挫折しやすい理由
社会人が資格試験に挑戦する場合、学生の頃とは違い、仕事や家庭、生活の制約があります。そのため、勉強を継続すること自体が大きなハードルとなります。
この章では、わたし自身の経験や周囲の受験生の様子から感じた、社会人が資格試験で挫折しやすい主な理由を整理します。
自分がどのタイプに当てはまるのかを知ることで、挫折を防ぐための対策を考える手がかりになります。
勉強時間を確保できない
多くの社会人が資格勉強で最初に直面するのは、十分な勉強時間の確保です。
仕事や家事、通勤などで1日の大半が埋まってしまい、思ったように机に向かう時間を作れません。
特に難関資格では数百時間以上の勉強時間が必要なので、計画的に時間を確保しないと途中で息切れしてしまいます。
どんなに効率よく勉強したとしても、一定の「勉強量」は土台として必要です。時間が確保できないと、勉強のリズムが崩れ、モチベーションも徐々に低下するでしょう。
「忙しくて無理だった」と挫折する原因になります。
モチベーションが続かない
資格勉強は長期戦になりやすく、最初はやる気に満ちていても、数週間や数か月続くとモチベーションが低下することがあります。
特に年1回しかないような試験がない資格では、合格までのゴールが遠く感じられ、先延ばしや妥協が増えてしまいます。
また、社会人は仕事と勉強を並行するので、疲れて帰宅したあと机に向かう気力が残っていないことも少なくありません。
このようなときに、いかにしてやる気を出すのかが多くの社会人にとって課題です。
孤独で支えがない
社会人は学生と違い、勉強仲間が周りにいないことが多く、孤独を感じやすい環境にあります。
家族や同僚が資格勉強に理解を示してくれる場合もありますが、多くの場合は勉強の進捗を共有できる仲間がいないため、モチベーションの維持が難しいです。
わたしも受験生時代は仕事と勉強しかしていなかったので、「孤独だなー」とよく感じていました。それでも、「やると決めたからやる」と言い聞かせ、なんとか乗り切っていました。
資格の学校に通っていたのも救いでした。周囲に同じ目標をもつ人がいることで、自分も頑張れていた部分はあったと思います。
孤独に耐えられるかどうかは、社会人が資格に挑戦するうえでの重要なポイントのひとつです。
計画を立てずに始めてしまう
資格勉強を始める前に、合格までの必要時間や自分の生活と照らし合わせて計画を立てない人も多くいます。わたしはこれこそが、挫折する大きな原因だと考えています。
いつも一番前の席で集中していたからか、資格の学校ではほかの受験生から「勉強の相談に乗ってほしい」と声をかけられることがよくありました。
話を聞くと「仕事が忙しくて勉強時間が確保できない」「子どもが小さくて自宅だと勉強に集中できない」などと嘆く人が多いのです。
スキマ時間の活用などのアドバイスはしたものの、「そもそも勉強を始める前になぜ考えなかったのか?」と感じざるを得ませんでした。
多くの社会人は、資格を取ろうと思い立つと、自分の生活スタイルや捻出可能な勉強時間を考える前に、前のめり気味に勉強を始めてしまいます。
しかし学生時代と違って資格の勉強は義務ではありませんし、けっこうなお金も必要です。
難易度が高い資格になれば仕事と食事・入浴以外のすべての時間を勉強に充てることも必要になるので、やみくもに始めては貴重な時間を無駄にしてしまいます。
社会人の資格受験で挫折を防ぐ方法
社会人が資格試験で挫折しないためには、計画的に勉強を進めることと、長期間続けられる工夫が必要です。
ここでは、わたし自身の経験を通じて効果的だと感じた具体的な方法を紹介します。
小さな習慣化を取り入れる
まずは、毎日少しずつでも机に向かう習慣を作ることが重要です。
- 起床後、家族が起きるまでの30分
- 帰宅後、食事や入浴までの30分
- 就寝前の30分 など
1回30分でもしっかり机に向かうことを習慣にすれば、積み重ねで大きな勉強時間に変わります。
勉強を習慣化し、忙しくても勉強ゼロ時間の日を作らないことが大切です。
最初から「1日4時間勉強しよう」と気合いを入れても挫折しやすいので、最初は1日20分~30分の勉強時間を確保するところから始めましょう。
習慣化してくると机に向かうのが当たり前になり、勉強に集中できる時間も徐々に延びていきます。
スキマ時間を有効活用する
仕事に家庭の用事にと忙しい社会人は、まとまった勉強時間を確保しにくいため、スキマ時間を活用することが重要です。
スキマ時間をうまく使うことで、まとまった時間が取れない日でも勉強量を維持できます。
特に暗記系の科目や用語の確認などは細切れの時間でも取り組みやすいのでおすすめです。
- 通勤電車の中
- 会社の昼休み
- 病院の待ち時間
- 入浴中
- 煮込み料理のタイマーが鳴るまでの時間 など
小さな時間も積み重なると大きな差になるため、日々の隙間時間をどう活用するかを意識することが挫折防止につながります。
中間ゴールを設定する
長期間の勉強では、最終目標だけを見ていると達成感が得られず、モチベーションが低下しやすくなります。
そこで、模試や章ごとの理解度チェックなど、短期的な中間ゴールを設定することが有効です。
わたしも社労士のスクールでは章ごとに定期テストがあり、成績上位者の名前が載った紙が全員に配布されていたので、まずは定期テストで満点を取って掲載されることを目標にやる気を維持していました。
中間ゴールを設定すると、自分の進捗が可視化され、計画の見直しもしやすくなります。
また、達成感を得ることで長期的なモチベーションを維持できるため、挫折しにくい状態を作ることができます。
勝算を確認した上で計画を立てる
資格勉強を始める前に、その試験の勝算を確認することは非常に重要です。
勝算というのは、「自分の頭で合格できるのか」ということではなく、「合格までに必要な勉強時間とお金を確保」し、「確実にやり遂げる算段をつけられる」のかということです。
たとえば、わたしは社労士の勉強を始める前に、1回の受験に必要な勉強時間を調べました。すると、最低でも1,000時間程度の勉強が必要だと分かりました。
社労士受験は1年に1回しかないので、単純計算でも1日3時間は毎日勉強し続けなければなりません(3時間×365日で1,095時間)。
とはいえ、1日3時間ならフルタイムで働きながらでも捻出可能です。仮に残業があったりで平日に3時間とれなくても、土日でその分多くやればいいので、1週間に21時間(3時間×7日)の勉強は実現可能な範囲だと思いました。
つまり、社労士という資格の勉強は、フルタイム勤務の自分でも現実的に取り組むことができ、その勉強時間を確保すれば合格も十分可能(勝算がある)と判断したのです。
一方で、わたしは社労士以外に司法書士の受験も検討していました。しかし司法書士の最低勉強時間は3,000時間だったので、1年で取得するには平日も含めて1日8時間以上、毎日勉強しなければなりません。
1日8時間の勉強は「フルタイムで働きながら取り組むのは現実的ではない」と判断し、司法書士ではなく社労士を受験することにしました。
なお、「自分の頭で合格できるのか」については、司法試験や公認会計士試験レベルの試験では考える必要があると思います。このレベルの試験は、論理的思考力や地頭が足りていないとそもそも勉強についていけない可能性が高いためです。
逆を言うと、そのレベル以外の試験なら、必要な勉強時間を投入して正しい方法で取り組めば、高学歴や頭脳明晰でなくても合格は可能だと思います。
事前に勝算を確認し、現実的に確保できる時間を把握しておくことで、勉強が停滞する前に軌道修正が可能です。社会人にとって、勉強の計画性は資格試験を最後までやり抜くうえで欠かせない要素です。
やると決めたらやる
資格試験に挑戦するからには、最初に「やる」と決めたことは必ずやり抜くという覚悟をもつことも大切です。
繰り返しになりますが、社会人の資格試験は義務ではないので、やりたくないなら最初からやらなければいいのです。
「今の生活では勉強時間の捻出が難しい」「資格よりも転職を優先させたい」など、現状と今やるべきことをしっかり判断し、やるか・やらないかを決めましょう。
そして、やると決めたら最後までやり抜くことが大切です。
お金と時間を無駄にしないためにも、まずは「やるか・やらないか」を決めるところで熟考しましょう。
本気ならスクールで友達をつくろうとしないこと
スクールに通うと、なぜか黒板から一番遠い後ろの席に座り、周囲の人と仲良くなろうとする受験生が一定数います。
しかし、勉強の本質は仲間作りではなく、合格のために集中して学ぶことです。
わたしはいつも一番前の席、空いていなければその後ろの席を確保していました。講師の話をよく聞き、黒板の内容をしっかり見て授業中も学ぶことが、合格までの近道だと考えていたからです。
最初から隣の席の人と仲良くなろうとする必要はありません。勉強を続けていれば、試験本番が近づくにつれて教室には「本気の人」だけが残ります。
そのときに自然と有益な情報交換や助け合いが生まれ、必要な仲間は後からできます。
最初から人間関係を優先してしまうと、集中力が分散し、勉強の効率も下がってしまいます。
資格勉強は自分との戦いです。周囲に流されず、自分で決めたことを最後までやり抜く覚悟を持つことが、挫折を防ぐ大きなポイントです。
まとめ
社会人が資格試験で挫折しないために大切なのは、受験まで勉強を継続する力を身につけることです。途中で諦める人の多くは、勉強時間の確保や勝算の確認を怠り、無理のある計画で始めてしまっています。
まずは自分の生活と目標を照らし合わせ、現実的に学習時間を確保できるかを確認することが重要です。また、資格勉強は長期戦なので、習慣化やスキマ時間の活用、短期的な中間ゴールを設定して、モチベーションを維持する工夫も欠かせません。
そして、「やるのか・やらないのか」を事前に決め、やると決めたらやり抜くことも大切です。周囲の状況に流されず、自分の決めたルールに従って集中することで、自然と必要な情報や仲間も後からついてきます。