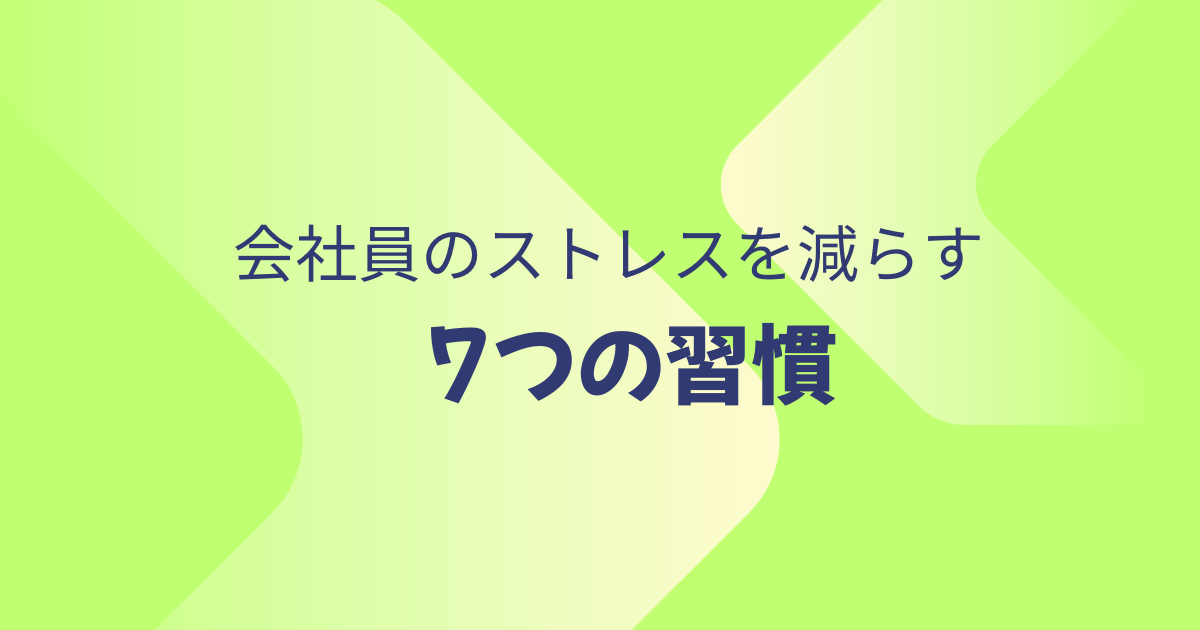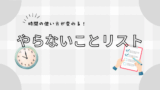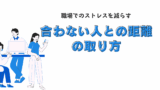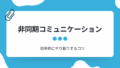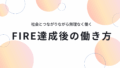長時間労働、人間関係、終わらないタスク……。会社員生活では、ストレスが積み重なるのが当たり前になっている方も多いのではないでしょうか?
わたし自身、10年の会社員経験の中でストレスが蓄積し、体調やメンタルを崩したこともありました。
この記事では、会社員時代にストレスを軽減できた習慣や考え方、働き方の見直し方をお伝えします。
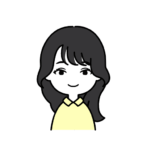
この記事はこんな方におすすめです。
- 毎日の仕事でストレスを感じやすい会社員の方
- 自分の働き方や心の余裕を見直したいと思っている方
- 心身が疲れており、早めに対処したい方
ストレスをためる会社員の共通点
会社員として働いていると、組織の中での役割や人間関係、時間的な制約などから、無意識のうちにストレスを溜め込んでしまうことがあります。
この章では、会社員として働く人の「ストレスを増やしやすい行動パターン」や「考え方の癖」を解説します。
以下の特徴に自分が当てはまっていると気づくだけでも、今後の働き方や習慣の見直しに役立つはずです。
自分で全部抱え込んでしまう
責任感が強く、真面目な人ほど「自分がやらなければ」と思い込みがちです。
本来はチームで分担すべき仕事も、「頼むのは悪い」「人に迷惑をかけたくない」と一人で背負い込んでしまいます。
このような思考が続くと、自分の限界を超えて働き続けてしまい、結果として心身ともに疲弊します。
「自分がなんとかするしかない」という姿勢が常態化すると、業務量もプレッシャーも増し、ストレスが慢性化する要因になってしまいます。
このような抱え込みのパターンは、周囲からは頼りがいのある人に見える一方で、自分を追い詰める温床にもなります。
無理をしてでも“ちゃんとやろう”とする
「どんな状況でもきちんとやるべきだ」という完璧主義の傾向も、ストレスの蓄積を招きます。
体調が悪くても出社し、予定が詰まっていても仕事を詰め込み、常に高いクオリティを目指す──そんな行動が無意識のうちに習慣化している人は多くいます。
この背景には、「手を抜いたら評価が下がる」「真面目にやっていないと思われたくない」といった不安や自己否定感が潜んでいるケースも少なくありません。
どんな仕事も100点で仕上げようとする姿勢は、一見プロ意識が高いようでいて、心身のリソースを消耗しやすい状態を作り出します。
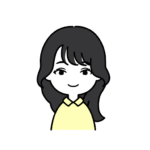
頑張りが効かなくなる前に、自分の「ちゃんとやらなければならない」という思考の癖に気づくことが重要です。
Noと言えない・断れない
頼まれたことを断れない人も、知らず知らずのうちにストレスを蓄積しがちです。
とくに職場の人間関係を気にするあまり、「断ったら嫌われるのでは」と不安になり、無理な依頼でも引き受けてしまうケースが少なくありません。
その結果、仕事が一極集中し、時間や気力がどんどん奪われていきます。
さらに、「頼めばやってくれる人」という印象を持たれてしまうと、負担が増える一方です。
こうした行動パターンがある人は、一見協調性があるようでいて、自分のキャパシティを守れなくなっている状態にあります。
Noと言えない状態が常態化すると、自分の意思を押し殺して仕事を続けることになり、精神的な摩耗を引き起こします。
自分の「感情」に鈍くなっている
忙しい日々の中で、自分の感情に対する感度が鈍くなっている人も少なくありません。
「疲れている」「つらい」「もう限界かも」といった気持ちを自覚する余裕がないまま、淡々と仕事をこなしてしまうのです。
これは、常に周囲の期待や評価に応えようとしすぎて、自分の内面に意識が向かなくなっていることが一因です。
気づけば怒りっぽくなったり、集中できなくなったりと、感情が不安定になっているサインが出ている場合もあります。
感情を無視し続けることで、ストレスが蓄積し、心身の不調を招くリスクが高まります。
「何を感じているのか」に気づけない状態は、ストレスへの早期対処を妨げる大きな障壁です。
会社員がストレスを減らすための習慣7選
ストレスを完全になくすことはできなくても、「ため込みにくくする習慣」を身につけることで、日々の働き方は大きく変わります。
とくに会社員は、時間・人間関係・役割の制約が多く、自由に動きづらい立場です。だからこそ、自分で選べる部分に意識を向けていくことが重要です。
この章では、会社員として働きながら実践できる「ストレスを減らすための具体的な習慣」を7つ紹介します。
「やらないことリスト」を作る
たとえば、「毎朝SNSをチェックしない」「無理に雑談に参加しない」「完璧を目指さない」など、自分にとって消耗しやすい行動を手放していきましょう。
最初は1つでも構いません。紙に書き出すことで、視覚的にも「手放していいこと」が見えてきます。
「やらないことリスト」は、頭の中を整理し、自分にとっての優先順位を明確にする効果があります。
減らすことで、余白が生まれ、必要なことに集中できるようになります。
すべてに全力投球するのではなく、「これは後回しでもいい」「これは他人に任せられる」と線を引けるようになると、気持ちもラクになります。
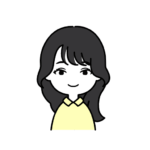
会社という組織にいると、どうしても「やらされること」が多くなりがちですが、“自分で選ぶ”感覚を取り戻すことが、ストレス対策の第一歩です。
「やらないことリスト」を作成するコツや効果は、以下の記事で詳しく書いています。
小さな“主導権”を取り戻す
会社員として働いていると、「自分ではコントロールできないこと」に日々向き合うことになります。スケジュール、業務内容、人間関係など、すべてが思い通りにいくわけではありません。
それでも、小さな部分で「自分で選ぶ・決める」習慣を意識するだけで、ストレスの感じ方は大きく変わってきます。
すべてを変えようとすると難しいですが、ほんの一部でも自分の意志で選ぶ時間や行動を取り戻すことで、受け身な働き方から抜け出すことができます。
たとえば、「朝の時間は絶対に自分のために使う」「昼休みはひとりで過ごす」「通勤中は音楽ではなく静かな時間をとる」など、小さな主導権を積み重ねることがポイントです。
自分の一日を自分で組み立てているという感覚は、想像以上に心を安定させます。
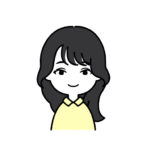
会社の都合にすべてを委ねず、「ここは自分で決めていい」と思える範囲を意図的に増やしていくことが、ストレスを減らす大きな助けになります。
マルチタスクをやめる
現代の働き方では、複数のタスクを同時にこなすことが求められがちです。
たとえば、電話を取りながらA案件の資料を読み、同時にB案件の進捗も確認する……といった働き方は、集中力を分散させるだけでなく、脳の疲労感を大きくします。
一方で、シングルタスク(1つの作業に集中する)に切り替えると、作業効率も上がり、ミスも減ります。
ストレスが溜まりやすい人ほど、「あれもこれも」と手をつけがちですが、それが逆効果になっていることは多々あります。
まずは、「今この30分だけは、この仕事に集中する」と決めることから始めましょう。
時間を区切って取り組むことで、達成感も得られやすくなり、精神的な満足度が上がります。
職場の人間関係は“割り切る”
会社員が抱えるストレスの大きな原因のひとつが、職場の人間関係です。
誰ともうまくやろうとしたり、すべての人に好かれようとしたりすると、精神的な負担はどんどん増えていきます。
しかし、会社という組織は価値観も働き方も異なる人たちの集合体です。
たとえば、「どうしても合わない人とは最低限の業務連絡だけにとどめる」「雑談の輪に無理して加わらないと決める」といった行動も、ひとつの選択です。
相手に変化を期待するより、自分の関わり方を変えるほうが、ストレスは格段に減ります。
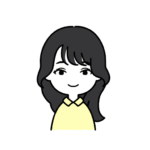
「深入りしない」「引きずらない」ための“距離感”を意識的に保つことが、長く働くうえでの心の守り方です。
職場にいる「合わない人」との距離の取り方については、以下の記事で詳しく書いています。
小さな「脱会社員」習慣でストレスを減らす
毎日の会社生活の中で感じるストレスの一因は、「会社のルールやペースに縛られている」という感覚です。
この感覚を和らげるためには、意識的に「会社の外の自分」を感じる時間や行動を増やすことが効果的です。
たとえば、週末や休日に副業や趣味、ボランティアなど会社以外の活動を始めてみるのも一つの方法です。
自分の専門分野や興味のあることについて学ぶ時間を作ることも、精神的な余裕につながります。
これらは「小さな脱会社員」と呼べる習慣です。会社の枠組みに縛られすぎず、自分の可能性を広げる感覚を育ててくれます。
自分自身の存在価値や自己肯定感を高め、会社でのストレスを軽減する助けにもなります。
「会社員である自分」と「個人としての自分」のバランスを意識的にとることで、精神的な安定を得やすくなります。
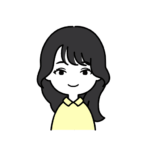
まずは月に1回でも、会社外の時間に自分が没頭できることを見つけることから始めてみましょう。
ストレスから距離を置く逃げ道を持っておく
ストレスが限界に達したとき、すぐに逃げられる選択肢があることは大きな安心感をもたらします。
たとえば、「しばらく休暇を取る」「部署異動を希望する」「転職の準備を少しずつ始める」といった具体的な逃げ道です。
逃げ道を持つことは弱さはなく、自己防衛のための賢い戦略です。
実際に行動に移さなくても、「いつでも動ける」と知っているだけで、現在のストレスが和らぐことも多くあります。
そのために、普段から自分の市場価値を把握し、スキルアップを続けておきましょう。情報収集をしておくことも大切です。
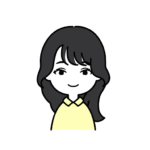
ストレスに押しつぶされる前に、無理のない範囲で逃げ道を考えておく習慣をつけましょう。
1日1回、自分の状態を言葉にする
たとえば、就業後や寝る前に「今日はどんな気分だったか」「どこが疲れているか」を一言で表現してみるだけでも変わります。
この習慣は、無意識にため込んでしまう感情に気づきをもたらし、自己理解を深めるきっかけになります。
言葉にすることでストレスが外に出ていく感覚を味わえ、心のモヤモヤを軽くできます。
方法はどんな形でもよいですが、日記やメモ、スマホのアプリを使って「記録」しておくと、自分のパターンやサインを把握しやすくなります。
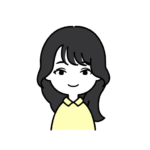
「忙しいから無理」と思わず、1分でもいいので自分と向き合う時間を持ちましょう。続けることで「自分の感情に鈍くなっている」状態を改善し、心の健康を保てます。
会社員がストレスフルな働き方を見直す思考法
日々のストレスを減らすには、行動面の改善だけでなく、根本的な「働き方」や「考え方」の見直しも欠かせません。
とくに会社員は、会社の都合や組織のルールに振り回されがちですが、心の余裕を取り戻すためには自分自身のマインドセットを整えることが重要です。
この章では、働き方に対する思考の切り替えや、長期的に続けられる習慣の作り方について解説します。
「会社中心」から「自分中心」へマインドを切り替える
多くの会社員は「会社の期待や評価」を最優先に考え、そこに自分の価値を見出そうとします。
しかし、この思考は自分の感情や体調を後回しにしやすく、結果としてストレスを増やしてしまいます。
具体的には、「自分がどう感じているか」「自分の健康や幸福を優先する」という視点を意識的に持つことです。
これは決して自己中心的になることではありません。自分の心身の状態を大切にすることで、結果的に仕事のパフォーマンスも向上するという考え方です。
まずは、自分の感覚や価値観を尊重し、「自分が納得できる働き方とは何か」を考える習慣をつけてみましょう。
小さな心の切り替えが、長い目で見て大きなストレス軽減につながります。
今すぐ会社を辞めなくても、心の主導権は取り戻せる
仕事のストレスに押しつぶされそうになると、「会社を辞めたい」と強く思うこともあります。
しかし、退職という大きな決断をしなくても、今の職場で心の主導権を取り戻すことは可能です。
たとえば、仕事の進め方や時間の使い方、気持ちの持ち方など、自分でコントロールできる範囲を意識的に広げていくことです。
優先順位の見直しや断る勇気、小さなリフレッシュ時間の設定など、日々の工夫を積み重ねることが心の余裕を作ります。
まずは自分の心のあり方を整えることから始めることがストレス対策の本質です。この意識の持ち方が、心の主導権を取り戻し、安定した働き方につながります。
働き方を根本から変えるには「小さな習慣の積み重ね」が必要
大きな決断や環境の変化は心理的負担も大きく、継続が難しいため、日常の中で取り入れやすい習慣を少しずつ増やしていくほうが長続きします。
たとえば、毎朝5分間のストレッチを習慣にする、仕事の合間に深呼吸をする、週に1回は自分の感情を振り返る時間を作るなど……。
これらの小さな習慣は、目に見える成果がすぐに出なくても、続けることで心身の状態を安定させ、ストレス耐性を高めていきます。
習慣化が進むと自信や自己肯定感もアップし、ストレスへの対処力が自然と強くなります。
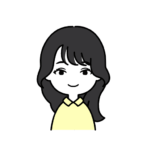
焦らずに「できることから少しずつ」を合言葉に、自分に合ったペースで取り組みましょう。
まとめ
会社員がストレスを軽減するポイントは、自分がコントロールできる範囲を明確にし、無理な負担を減らすことです。とくに「やらないこと」を決めて主導権を取り戻す姿勢が欠かせません。加えて、シングルタスクの集中や人間関係の割り切りも心の余裕につながります。
そして日々の小さな習慣で心の声に気づき、心身のバランスを整えることが、長期的なストレス対策になります。