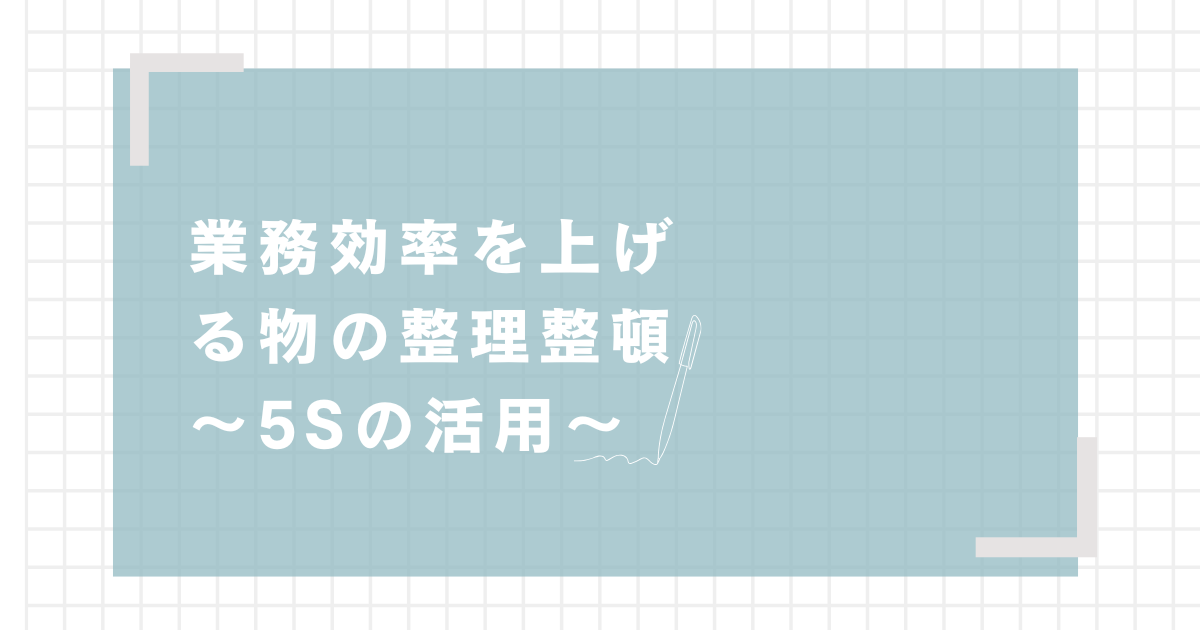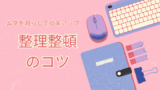業務を効率化し、残業を減らすためには、整理整頓が欠かせません。職場での無駄な動きや探し物の時間を減らし、スムーズに仕事を進めるために、体系的な整理整頓を行いましょう。
整理整頓には「物」と「情報」の整理がありますが、この記事では「物」の整理整頓について解説します。職場環境の改善に役立つ「5S(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)」を活用した、具体的な手順を見ていきましょう。
整理整頓をするメリット
整理整頓が習慣化していない方は、整理整頓をするメリットを理解することが大切です。整理整頓を実践することで、以下のようなメリットがあります。
- 時間を節約できる:探し物の時間やムダな動き、重複作業などの時間が減ります。
- 生産性が向上する:必要なものがすぐに取り出せるため、作業スピードが上がります。
- ミスを防止できる:不要なものを取り除くことで、誤った資料や古い情報を使うリスクが減ります。
- 働く環境が改善できる:スッキリとした環境だと集中して気持ちよく働くことができ、モチベーション向上にもつながります。
これらの結果、残業も削減できます。
5Sに基づいた整理整頓の流れ
職場の整理整頓を進めるには、「5S」の考え方が役立ちます。5Sとは、「整理・整頓・清掃・清潔・しつけ」の5つの要素からなる職場環境の改善手法です。もともとは日本の製造業で生まれた概念ですが、オフィスワークにも応用でき、業務効率の向上やミスの防止に役立ちます。職場全体で整理整頓するときに使われることが多いですが、個人単位で整理整頓するときにも活用できます。
整理|不要なものを捨てる
まずは「整理」です。使用頻度の低いものや不要な資料を処分し、本当に必要なものだけを残します。
ポイントは、1年以上使っていないものは処分を検討することです。捨てるべきか迷った場合は「今後の業務で本当に必要か?」を基準に判断しましょう。
整頓|必要なものを使いやすく配置する
次に「整頓」です。整頓では、使用頻度に応じて物の置き場所を決め、配置します。個人単位で整頓する場合は、自分が最も使いやすい配置にしましょう。
ポイントは、よく使うものは手の届く範囲に置くことです。たとえば頻繁に使うペンはデスク上のペン立てに、週に1回程度しか使わないはさみは引き出しの中に、といった形で物の置き場所を決めましょう。自分の中で収納場所を決めておくことで、いつでも迷わず、すぐに取り出せるようになります。

物の「住所」を決めるイメージです。
収納する物が多い場合は、収納場所にラベリングすると、一目で収納場所を把握できます。引き出しに「はさみ、カッター」のようなラベルを貼るといいですね。
清掃|常にきれいな状態を保つ
続いては「清掃」です。毎日決まった時間など定期的に清掃を行い、働く場所を清潔に保ちます。
個人単位で5Sを実施する場合は、デスク周りを毎日片付け・清掃する習慣をつけましょう。始業前や就業後など、ルーティン的にデスク周りを拭いたりファイルを整理したりするのがおすすめです。
また、掃除をしながら、機器の状態もチェックしましょう。常にチェックすることで、機器の汚れや異常などを早期に発見できます。
清潔|整理・整頓・清掃を維持する
「清潔」では、ここまでの整理・整頓・清掃を維持し、快適に働ける環境をつくります。
ポイントは、自分の中でルールを決め、そのルールに従って快適な環境を維持することです。「毎週金曜日には不要な書類がないかチェックする」みたいなことですね。
ルールは定期的にチェックし、必要に応じて改善しましょう。
しつけ|整理整頓の習慣を定着させる
「しつけ」は、継続する仕組みをつくることです。チームでのしつけの場合、メンバー全員に5Sを浸透させる必要がありますが、個人で実践する場合は自分でルールを守り、継続できる仕組みをつくります。
たとえばTo Do リストに「整理整頓」のタスクを追加するといったことです。
まとめ
整理整頓は、業務の効率化と残業削減に直結する重要な取り組みです。5S(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)を実践することで、スムーズな業務環境を整えることができます。
「デスク周りが散らかっている」「探し物に時間を取られる」と感じる方は、まずは不要なものを処分する整理から始めてみましょう。小さな積み重ねが、業務の効率化につながります。ぜひ今日から実践してみてください。